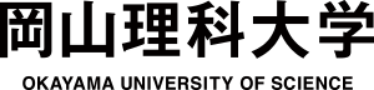-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
70理学系化学周期表と元素のひみつ基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験全ての物質は元素からできています。私たちも物質なので、私たち自身も元素からできています。物質の世界を理解するためには、水素、炭素、窒素、酸素といった日本語元素名を知っていると便利です。では世界の人々と物質の話をするためには、外国語の元素名も知らなければいけないのでしょうか。元素名は、元素記号という世界共通の記号で書き表すことができます。その元素記号を、ある法則にしたがって美しく並べた表のことを周期表といいます。楽しい周期表のお話をしましょう。化学の楽しさ・奥深さを伝えます。演示実験あり。 https://www.gsakane.com/visiting.html
-
71理学系化学小さすぎる原子・分子・電子の世界基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験私たちが暮らす地球は大きすぎて、球であることは実感できません。しかし地球儀を見たり触ったり、宇宙から撮影した地球の画像を見れば、地球が丸いことを想像して実感できます。一方、私たちが暮らす世界は物質でできています。物質はつぶつぶの原子でできていますが、小さすぎて原子を粒として実感することは困難です。この講義・実験では、小さすぎて実感しにくい原子・分子・電子の不思議な世界を知り、想像して実感できるようにします。ミクロの不思議な世界を三次元可視化して示し、電気伝導、色、磁性の本質を伝えます。演示実験・生徒実験あり。 https://www.gsakane.com/visiting.html
-
72理学系物理学電子の軌道を三次元可視化して見てみよう!基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験「化学基礎」にでてくる「電子の軌道」を三次元可視化して遊びましょう!K殻、L殻、M殻と1s軌道、2s軌道、2p軌道の関係も納得できるように説明します。5g軌道、6h軌道、7i軌道まで見てしまいましょう!原子軌道をガラス内部にレーザー彫刻したものを生徒様お一人一つずつ触っていただき、立体的な原子軌道を実感していただきます。もし、ごく普通のWindowsパソコンをご用意いただければ、周期表全ての元素の原子軌道、高校の教科書に出てくる分子の分子軌道を三次元可視化できる「教育用分子軌道計算システムeduDV」をインストールいたします。プログラムは(秀丸エディタがシェアウェアであることを除き)無償のもので、何台でもインストールしていただます。 https://www.dvxa.org/
-
218理学系自然科学磁石のひみつ基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験スチール缶は磁石にくっつきますがアルミ缶は磁石にくっつきません。しかし本当にアルミニウムは磁石にくっつかないのでしょうか。実は世の中の物質はすべて、磁石が近づいた時にはくっつこうとするか、逃げようとするかのどちらかです。電子がいない物質はないので、磁石が近づいた時に何も起こらない物質はありません。室温で磁石の上で空中浮遊する黒い物質、天空の城ラピュタの飛行石のように永遠に空中浮遊して回転する黄金色の立方体、ひっくり返しても決して反発することのないくっつくだけの不思議な磁石、ウニのようなトゲトゲになる液体の磁石、重力に逆らう磁石球、突然加速する磁石球など、磁石に関するたくさんの実験を楽しみましょう。班単位での生徒実験を中心とした授業です。https://www.gsakane.com/visiting.html
-
258人文・社会科学系人類・歴史・文化学吉備の楯築弥生墳丘墓と出雲の西谷墳墓群
~過去から未来までの時間軸における人間と物質~基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義人類は古代から現代まで、自然から取り出した物質を利用して文明を築いてきました。石器時代、青銅器時代、鉄器時代、そして現在はケイ素時代かもしれません。岡山県倉敷市の双方中円墳型の楯築弥生墳丘墓の水銀朱、島根県出雲市の西谷墳墓群の四隅突出型墳丘墓から出土した勾玉、岡山理科大学の至近距離にある前方後円墳・一本松古墳から出土した鉄槌(かなづち)、鉄鉗(かなはし)など、身近な遺跡・古墳から出土した物質を紹介します。人類の社会の歴史を物質の視点から解釈し、未来の社会を物質の視点から考えることを目指す授業です。物質に関する演示実験、生徒実験も行います。 https://www.gsakane.com/
-
259工学系応用化学草木染を体験してみよう!
~植物色素・昆虫色素で布を染める技術と原理~基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験飛鳥時代、聖徳太子が制定した冠位十二階では、位によって冠の色が定められていました。布を目的の色に染める、その染色の方法は平安時代の延喜式にも記されています。草木から得られる色素で布を染めるとき、金属イオンを含む灰などを加えることがあります。これは媒染と呼ばれる工程です。同じ色素でも媒染剤の種類(金属イオンの種類)を変えると、染め色が変わってきます。媒染工程の本質は色素を配位子とする金属錯体の生成です。同じ色素(配位子)でも金属イオンの種類が異なれば、生成する錯体はそれぞれ異なります。この授業では玉ねぎの皮からとれるケルセチン、コチニールカイガラムシからとれるカルミン酸を題材に、天然染料で布を染める技術と原理についてお話しします。時間があれば、玉ねぎの皮茶とミョウバンで布を染めてみましょう! https://www.gsakane.com/mugen/
-
265教育学教育学児童・生徒の好奇心を刺激する科学おもちゃ
~見て触って実感する理科・算数の基礎概念~基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義スマートフォンやタブレットで動画を見る時間が多い現代、児童・生徒の原体験が不足している可能性があります。実際に手に取って見て触って、五感で体感した驚きと発見こそが児童・生徒の原体験となります。貴校に、普通教室で安全に遊べる科学おもちゃをたくさん持っていきます。将来、学校の先生になってもいいかもと思っている高校生の皆様に、まずはご自身で遊んでいただき、そこで得た驚きと発見を児童・生徒にどう伝えるのが効果的か、一緒に考えていきましょう。私は仮説社の月刊『たのしい授業』で1年間(12回)、科学おもちゃを紹介する記事を連載しました。その連載で紹介した科学おもちゃも全部、貴校に持っていきます。 https://www.gsakane.com/eduExp/