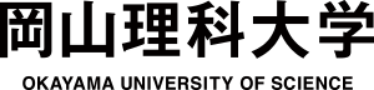-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
133工学系機械工学SDGsとエコマテリアル機械システム工学科
教授 中川 惠友講義近年、地球温暖化対策と関連して世界的にCO2排出量削減が緊急の課題となっており、また、持続可能社会の発展(SDGs)を目的として地球資源の有効利用も重要となっています。軽量でリサイクル性の高いアルミニウム合金などの軽合金材料はエコマテリアル(地球環境に配慮した材料)として注目されています。本講義では、機械製品、エレクトロニクス、輸送機器、生活製品など多方面にてエコマテリアルの果たす役割をわかりやすく解説します。
-
134工学系機械工学工業を支える様々な材料の話機械システム工学科
教授 清水 一郎講義私たちの身の回りにある様々な機械や構造物は、全て固体材料でできていますが,使われている材料は物によって大きく異なります。実際のものづくりの場面では、どのように判断して材料を選んでいるのでしょうか?この講義では、様々な固体材料を紹介した後、材料の選び方やその基準について、例を挙げながら説明します。
-
136工学系機械工学機械製図のおもしろさ機械システム工学科
教授 中井 賢治講義実験飛行機や自動車などの工業用製品の安全設計のためには、それを構成する各部品の形状寸法を正しく決める必要があります。その形状寸法を基に実際に部品を製作をしなければいけませんが、複雑な形状寸法を言葉だけで製作者に伝えることは困難です。もし伝えることができたとしても、全く別の形状になってしまうかもしれません。このようなことが起こらないように、どのような形状を製作してほしいか図面として残す必要があります。ただ、自分では完璧な図面を描いたつもりでも、他の人が見た時にそれを理解できなければいけません。そのため、図面を描く人と見る人が共通の認識を持てるように、日本では日本工業規格(JIS)に従って図面の読み書きが行われています。実際に簡単な図面をJISに従って描いてもらい、機械製図のおもしろさを一緒に実感したいと思います。
-
215工学系機械工学身近にあるモーターはなぜ回る?機械システム工学科
教授 吉田 浩治講義私たちの身の回りには電気によるモーターと呼ばれている物で動作している機械が沢山あります。例えば、電気自動車、扇風機、コンピュータのファン、プラモデルなど。よく使われている電気のモーターには、コンセントに繋ぐと回りだす交流モーターと乾電池に繋ぐと回りだす直流モーターがあります。この講義では、主としてこの2種類のモーターがどうして回転するのかを説明します。
-
227工学系機械工学くらしを支える流体力学機械システム工学科
准教授 岩野 耕治講義流体力学は、空気や水の動きを解き明かし、工学や環境問題の解決に役立つ学問です。私たちが普段使っている電気も、その多くが流体の力を利用して作られています。例えば、火力発電や原子力発電では、高温の蒸気でタービンを回し、風力発電では風の力で羽根(ブレード)を動かし、水力発電では川やダムの水の流れでタービンを回します。このように、流体の動きをうまくコントロールすることは、エネルギーを効率よく生み出すために欠かせません。さらに、この流体力学は自動車や飛行機の設計にも活用され、空気の流れを調整することで燃費を向上させたり、飛行機がスムーズに飛べるようにしたりしています。また、台風や線状降水帯による大雨などの自然災害を予測し、防ぐためにも流体の研究はとても重要です。本講義では、このように私たちの生活と深く関わる流体力学について、わかりやすく説明します。
-
228工学系機械工学貨幣の作り方から「ものづくり」を学ぶ機械システム工学科
准教授 寺野 元規講義自動車や飛行機,身の回りの製品の作り方を考えたことはありますか?貨幣(お金)と自動車などの部品の製造方法は同じ技術です.特に日本の貨幣は諸外国よりも精巧であり,日本の「ものづくり」技術の高さがうかがえます.この講義では,貨幣の変遷・作り方を通して,現在の日本を支える「ものづくり」を説明します.