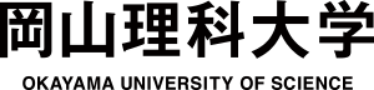-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
204獣医系獣医学・生物学健康寿命を考える~生活習慣病編~獣医学科
講師 向田 昌司講義生活習慣病とは、高血圧や糖尿病、脂質異常症など、私たちの日々の生活習慣が深く関わる病気のことです。これらは健康への影響が大きいだけでなく、医療費の増加や死亡原因の上位を占めるなど、社会的にも重要な問題となっています。
本講義では、生活習慣病の基本的な内容を解説し、最新の話題や先端の研究を紹介します。動物を使った研究が人間の健康維持や治療にどのように役立っているのか、薬が病気の予防や治療にどのように貢献しているのかにも触れていきます。
講義を通して、自分自身やご家族、身近な動物の健康を見つめ直すきっかけにしていただければ幸いです。 -
205獣医系獣医学ホルモンと行動獣医学科
教授 村田 拓也講義体内では、たくさんのホルモンが、様々なはたらきをしています。ホルモンは、ホルモンをつくる細胞(内分泌細胞)から血液中に分泌され、からだ中をめぐって、特定の細胞(標的細胞)にはたらきます。ホルモンの分泌が、多すぎても、少なすぎても、病気になることがあります。また、ホルモンは、動物の様々な行動にも関わっています。そのような行動に関わっているホルモンについて説明します。
-
206獣医系公衆衛生学疫学の考え方獣医学科
准教授 高橋 秀和講義疫学とは、集団を対象として疾病の頻度・分布、疾病に影響を与える要因やその対策を明らかにする学問のことです。疫学は古くは伝染病の拡大防止、現在では根拠に基づく医療など公衆衛生や医学において大切な役割を果たしています。疫学・統計学による因果関係の解明についてなるべく分かりやすく説明します。
-
207獣医系獣医学犬の皮膚疾患獣医学科
准教授 松田 彬講義犬にも皮膚病があることはご存じでしょうか?獣医師は大学でどのような検査を行って診断し、どうやって治療するかを学びます。この講義では、動物病院で行われている検査や治療についてわかりやすく説明します。またシャンプーの方法など、日常的なケアについても紹介します。
-
208獣医系獣医学獣医学の世界で学ぶ生物物理学とは何?獣医学科
教授 斉藤 真也講義岡山理科大学獣医学科の1年生は生物物理学が必修になっていますが、高校時代に生物学と物理学の両方を選択した学生はあまりいない様です。獣医学科の生物物理学では、酵素反応やイオンの流れ、あるいはタンパク質の構築と変性など生物学で扱うトピックが、物理学的な視点によってより深く理解できることを学びます。
-
209理学系生命科学侵入者(異物)に対する生体防御機能医療技術学科
講師 松永 望講義私たちの体内は実に様々な手段で日々、数多の外来異物(ウイルス、細菌など)から自己を防衛しています。その防衛方法は実に巧妙かつ複雑なシステムを構築しています。もし、異物が体内に侵入した際は、そこはまるで壮大な戦場と化します(殲滅戦、情報戦、etc)。本講義では宿主側がどのような防衛手段を用いているのか?、また侵入者側がどのような手段を用いて侵入し、生存を図るのか?、双方の視点から解説していきます。
-
209獣医系獣医学動物の死因究明獣医学科
講師 中村 進一講義病理解剖というと、どのようなイメージをもっていますか?残酷、怖い、汚いなどあまり良い印象はないのではないでしょうか。実は解剖をすることで、多くのことを学ぶことができます。亡くなった動物の解剖によって、死因は何だったのか、体の中で何が起きていたのか、生前の診断は正しかったのか、予想しなかった病気はなかったのか、といったことを明らかにすることができます。死因を明らかにすることで、飼い主は死を受け入れ納得することにつながり、治療にあたった獣医師は診断や治療の検証をすることができます。それだけでなく、後に残された多くの命を助けることも可能です。この講義では、様々な動物の死因究明について説明します。「死」が身近な存在でなくなった今、「死」から「生」の大切さを考えてみませんか?
-
210農・医療・生活科学系医療資格臨床検査技師について知ろう!! 医療技術学科
講師 富安 聡講義病院では医師をはじめとする多くの医療従事者が働いています。臨床検査技師もそううちの1職種です。臨床検査は、医師の診断・治療に必要不可欠なものです。講義では、臨床検査技師の業務である臨床検査とはどんなものなのか、そして臨床検査技師が病院を含めてどんなところで活躍しているのかを紹介します。
-
211農・医療・生活科学系医療技術病院における外来診療の考え方と現状医療技術学科
教授 木場崇剛講義君たちが病院にかかった際に、医師は何を考えて診療を行っているかをわかりやすく解説します。将来、医療職を考えている君にも大変役立つと思います。
-
212理学系生命科学遺伝子多型と遺伝子診断について医療技術学科
教授 橋川 直也講義近年、人の疾病に関する分子レベルでの理解が進み、罹患のリスク、薬の作用・副作用の現れ方の違いが、遺伝子の違いによることが明らかになってきました。その遺伝子の違いには、人口の1%以上の頻度で存在する遺伝子の変異型である遺伝子多型というものがあります。この講義では遺伝子多型と遺伝子診断、さらに遺伝子治療について解説します。
-
213理学系生命科学私たちの感じる世界:脳が描く現実医療技術学科
教授 橋川 成美講義日常生活を送る上で欠かせないのが、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚といった五感です。これらの感覚は外部の刺激を生体内で電気信号に変換し、脳に送ることで、私たちは外界を感じることができます。では、どの脳部位がどのような信号を受け取るのでしょうか。また、信号が適切に入力されない場合、私たちの感じている世界はどのように変化するのでしょうか。
-
214農・医療・生活科学系医療技術患者中心の医療の構築:EBM(根拠に基づいた医療)とNBM(物語と対話に基づいた医療)について医療技術学科
教授 片岡 健講義現代医療のトレンドであるEBM(根拠に基づいた医療)について、その考え方と必要性を解説します。また、対となるNBM(物語と対話に基づいた医療)にも触れながら、患者中心の医療をどう構築するかについて考えます。さらに、医師だけでなく臨床検査技師・臨床工学技士などの医療技術者がEBM・NBMに関わるために、高校・大学で何を身につけるべきかについても説明します。
-
215工学系機械工学身近にあるモーターはなぜ回る?機械システム工学科
教授 吉田 浩治講義私たちの身の回りには電気によるモーターと呼ばれている物で動作している機械が沢山あります。例えば、電気自動車、扇風機、コンピュータのファン、プラモデルなど。よく使われている電気のモーターには、コンセントに繋ぐと回りだす交流モーターと乾電池に繋ぐと回りだす直流モーターがあります。この講義では、主としてこの2種類のモーターがどうして回転するのかを説明します。
-
217情報系統計科学視聴率の数理基盤教育センター
教授 中川 重和講義視聴率調査を行う際の統計的理論を解説します.
標本調査,正規分布,中心極限定理などがキーワードになります. -
218理学系自然科学磁石のひみつ基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験スチール缶は磁石にくっつきますがアルミ缶は磁石にくっつきません。しかし本当にアルミニウムは磁石にくっつかないのでしょうか。実は世の中の物質はすべて、磁石が近づいた時にはくっつこうとするか、逃げようとするかのどちらかです。電子がいない物質はないので、磁石が近づいた時に何も起こらない物質はありません。室温で磁石の上で空中浮遊する黒い物質、天空の城ラピュタの飛行石のように永遠に空中浮遊して回転する黄金色の立方体、ひっくり返しても決して反発することのないくっつくだけの不思議な磁石、ウニのようなトゲトゲになる液体の磁石、重力に逆らう磁石球、突然加速する磁石球など、磁石に関するたくさんの実験を楽しみましょう。班単位での生徒実験を中心とした授業です。https://www.gsakane.com/visiting.html
-
219理学系数学グラフを使った位相幾何学入門基礎理学科
准教授 稲葉 和正講義グラフと呼ばれる点と、それらをつなぐ線でできる図形の性質および、グラフを応用して解ける問題について紹介します。またグラフの性質を通して、位相幾何学の考え方を紹介します。
-
220理学系自然科学河川水・湖沼水の化学分析基礎理学科
教授 杉山 裕子講義河川水や湖沼水に含まれている化学成分は、様々な手法を用いて測定されます。サンプルを採取する(サンプリング)ところから化学分析は始まっています。「水をはかる」ために必要な準備、実際のサンプリング法、測定法、得られる結果の例を講義し、実際に大学で行われている調査についてもお話しします。
-
221理学系環境科学生物指標を用いた現在の瀬戸内海の環境評価基礎理学科
教授 齋藤 達昭講義実験瀬戸内海の環境を、環境指標生物リストを用いて生物種の存在の有無や生物種の存在量を調査することによって評価していくという内容の講義を行います。この講義では、化学的な分析を用いた環境評価法の紹介と環境指標生物リストを用いた環境評価法のやり方、両者による評価を行ったときの類似性について行います。また、身につけておきたい磯観察を安全に行う為の基礎知識についても講義します。。
なお、日程等があえば、座学のみでなく半日~一日程度の野外実習を取り入れたより実践的なメニューにも対応可能です。 -
222理学系自然科学有機化学 ~無限の可能性とSDGsへの貢献~基礎理学科
教授 東村 秀之講義有機化学は、炭素結合の多様性により無限の可能性があることを、実習を通して実感してもらいます。また、環境に優しい方法で、エレクトロニクス分野やエネルギー分野の先端有機材料の研究について紹介します。
-
223理学系生物学ゴリラは子どもを叱らない動物学科
教授 竹ノ下 祐二講義アフリカ大型類人猿であるゴリラは、DNAのおよそ95%が現生人類と共通しており、彼らの心や社会のありようには、私たちヒトと多くの共通点が見られます。しかし、ゴリラの育児のあり方は、現代社会のそれとはずいぶん違います。そして、なぜヒトとゴリラの育児はこうも違うのでしょうか?それとも、もしかしてヒトの本来の育児はむしろゴリラのそれに近いもので、現代日本社会の育児論が「異常」なのでしょうか。そんなことを考えてみたいと思います。