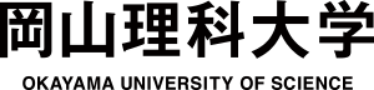-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
141工学系電気・電子工学環境とエネルギー
「電気自動車と太陽光発電システムの技術」電気電子システム学科
教授 笠 展幸講義実験電気自動車では電池のエネルギーを有効に使うために、自動車の駆動用モータを制御するユニットには様々な工夫がされています。その技術について家電・鉄道の省エネルギー技術の歴史を含めて紹介します。
-
142工学系電気・電子工学ダイオードとトランジスタ
―身近な電子回路―電気電子システム学科
准教授 道西 博行講義実験半導体と呼ばれる素子の中で、ダイオードとトランジスタをとりあげ、身近に用いられている電子回路について簡単に解説します。
また、受講者にも実際にブレッドボードを用いて電子回路を作製していただきます。
※尚、ハンダ付けを行いませんので、普通教室(講義室)で実施できます。 -
143工学系電気・電子工学電力コンディショニング電気電子システム学科
准教授 麻原 寛之講義実験ここ数年間、大規模自然災害に関するニュースを多く耳にするようになりました。先進国の間では、二酸化炭素の排出量を減らすことを念頭に、クリーンエネルギー発電に係る技術開発が急ピッチで進められています。本講義では、クリーンエネルギー発電デバイスから得られる電力を有効に利用するための電力コンディショニング技術について、基本的な発電システムの構成、回路動作、回路設計、産学連携した取組等を紹介します。
-
144工学系電気・電子工学非線形応用電気電子システム学科
准教授 荒井 伸太郎講義自然界で生じる非線形現象であるカオスや確率共鳴を工学に応用する研究は古くからあり、それらの研究について紹介します。
-
145工学系情報工学人工知能技術情報工学科
教授 片山 謙吾講義人間の持つ知的な能力を機械(コンピュータ,システム,ロボットなど)に持たせることによって、より快適に便利で使いやすいソフトウェアやシステムの開発が進められています。そのような研究・技術は,人工知能(Artificial Intelligence: AI)と呼ばれ、20世紀半ばから盛んに研究されており、我々は身近なところで様々なAI技術を利用しています。本講義では、AIの歴史やAIの問題、具体的なAI技術の例を紹介しながら、AIの面白さや重要性について授業します。
-
146工学系情報工学文字パターンの認識情報工学科
教授 島田 恭宏講義文字パターンのコンピュータによる認識処理は、古くから取り組まれてきました(実用化された有名な例では、郵便番号による郵便物の仕分け機があります)。本講義では、パターン認識のための最も基本的考え方を説明します。そして簡単な手計算によるパターン認識処理を体験してみましょう(筆記用具をご持参ください)。
-
147工学系情報工学ICチップを解剖する情報工学科
准教授 近藤 真史講義スマートフォンなどの電子機器を分解すると、数多くのICチップ(集積回路)がその姿を現します。これらICチップの中には、億単位の回路素子が圧縮されており、さらに1秒間に数億回の処理を行っています。本講義では、私たち人間とは大きさも速度もスケールが異なるICチップについて、その作り方と今後の発展について分かり易く解説します。
-
148工学系情報工学災害に強いまちづくりとシミュレーション情報工学科
教授 西川 憲明講義ひとたび大規模災害が発生すると、人が集まるスペース、ターミナル駅や商業施設などから、その場にいる人々をどのように避難させればよいかが重要になります。しかし、防災訓練をするにしても、多くの人々を対象に実施することは現実的には不可能です。本講義では、シミュレーションというバーチャルな社会実験を通じて、突発的災害に対する人々の安全・安心を守る取り組みについて紹介します。
-
148工学系応用化学髪の毛サイズの化学工場応用化学科
教授 平野 博之講義直径約100ミクロン(0.1 mm)の髪の毛ほどの微小なスケールでは、化学工場で行われているさまざまな反応・操作を高効率で行うことができたり、大きなスケールでは見たことがない流れが出現したりします。こうした技術を用いると、化学工場を小さくすることができたり、環境負荷も低減することができます。本講義では、動画などの実験結果を交えてこれらの事柄を講述します。
※ポインターのお貸しと、薄暗くなる普通教室の準備をお願いいたします。 -
149工学系応用化学塩水を用いた太陽光の蓄熱応用化学科
教授 平野 博之講義塩水と水を用いると、太陽光のエネルギーを熱として蓄熱することができます。この講義では、実験の結果とシミュレーションの結果を用いて、蓄熱のしくみについて解説します。
-
149工学系情報工学3Dレーザスキャンの技術とその応用情報工学科
教授 島田 英之講義私たちの身の回りでは、小さな部品の計測から広範囲の地形の計測まで、多くの分野でさまざまなタイプのレーザスキャナが活用されています。本講義では、レーザスキャナがどのような原理で3D計測を行うのか、計測するとどのような3Dデータが得られるのかについて解説します。そして、レーザスキャナで得た3Dデータを分析するとどのような情報や映像が得られ、社会にどう役立つのかについて、車に搭載したレーザスキャナで計測したデータを題材にやさしくお話しします。
-
150工学系応用化学石鹸や金属ナノ微粒子などのナノ物質の世界応用化学科
教授 竹崎 誠講義実験石鹸の成分によるミセルや金属ナノ粒子の性質等のナノ物質の世界についての説明・演示実験を行います。
-
150工学系情報工学ネットワークの基礎とインターネット情報工学科
助教 川畑 宣之講義皆さんのスマートフォンは、時間や場所を問わず、友達とメッセージや画像をやり取りしたり、動画を見たりすることができます。これは、スマートフォンが常にインターネットに接続されているからこそ可能なことです。では、そもそもインターネットとは何なのでしょうか?本講義では、インターネットという巨大なネットワークを実現するための基本的な技術や、インターネットの仕組みについて解説します。さらに、皆さんが普段使っているWi-Fiや5Gなど、インターネットに接続するための身近な技術についても見ていきます。
-
151工学系応用化学界面活性剤の話応用化学科
教授 森山 佳子講義界面活性剤(セッケンは界面活性剤の1種)は、水にも油にも溶けることのできる不思議な物質です。界面活性剤は、分子同士が集まって集合体を形成したり、種々の界面(例えば、液体の表面)に吸着したりという特異な性質をもっていて、洗剤だけでなく、食品や医薬品などさまざまなところで利用されています。この講義では、界面活性剤の特徴や機能を中心に話をします。
-
151工学系情報工学無線通信やストレージに使われる誤り訂正符号情報工学科
准教授 麻谷 淳講義みなさん、スマートフォンで友達とメッセージをやりとりしたり、ネットで動画を見たり、クラウドに写真を保存したりすることは日常的ですよね。でも、電波が弱かったり、データが壊れてしまったらどうなるでしょう?そんなとき、見えないところで活躍するのが「誤り訂正符号」です。誤り訂正符号は、データが壊れたり、一部が欠けても、「元の形」に復元できる仕組みのことです。例えば、ジグソーパズルが1ピース無くても全体の絵が分かるようなものです。実はこの技術、人工衛星や宇宙探査、さらには最新の量子コンピュータにも使われています。私たちの生活を支えるだけでなく、科学の最前線でも大活躍しています。誤り訂正符号の仕組みを知ると、身の回りの技術がどれだけすごいかに気づくはずです。この講義では、さらに深い仕組みや実例を一緒に学びましょう!
-
152工学系応用化学それってホントに環境にやさしいの?
-化学の目でエコを考えてみよう-応用化学科
教授 折田 明浩講義天然素材から作ったセッケンや洗剤,電気自動車にハイブリッド車、太陽電池など世の中には「環境にやさしい」ものや、「エコ」なものが溢れています。でも、ホントに環境にやさしいのでしょうか? どのくらいエコなのでしょうか? じっくり観察すると、「環境にやさしく見えるもの」が実は環境破壊していたり,「エコに見えるもの」が、それ程エコでなかったり... 世の中に溢れている「エコ」を化学の目から一緒に考えてみませんか。
-
152工学系情報工学情報工学科で学べること ―並列処理技術とその応用を中心として―工学部情報工学科
准教授 上嶋 明講義情報工学は現代社会で欠かせない基幹技術分野の一つです。本講義では、本学の工学部情報工学科で学べる授業の内容を簡単に紹介します。特に、ディープラーニングや物理シミュレーションをはじめとする大規模計算を可能にする技術として近年必須となった並列処理の基礎と、GPU(グラフィックス・プロセシング・ユニット)やスーパーコンピュータの原理について説明します。また、情報工学の技術を応用して最近の学生が取り組んだプロジェクトや修士研究・卒業研究の内容と成果について紹介します。
-
153工学系応用化学創薬:毒と薬
-えっ! 猛毒から薬ができるんですか?-応用化学科
教授 折田 明浩講義
1943年12月、イタリア南部のバーリ港がドイツ空軍の爆撃を受けました。この時、軽度の火傷にも関わらず、なぜか静かに息を引き取る兵士が多く見られました。調査の結果,実は爆撃を受けたジョン・ハーヴェイ号には100トンもの毒ガスが積載されており、このことを知らなかった兵士が,毒ガスを浴びたり吸い込んだして亡くなったことが判明しました。この出来事は「バーリ港の悲劇」とよばれています.この時,兵士を治療したお医者さんは,兵士のリンパ球や白血球が大幅に減少していることに気付き,「毒ガスがリンパ種や白血病の治療に利用できるのでは?」と閃きました。こうした先人たちの足跡をたどりながら,気が遠くなるような努力と閃き,そして幸運に支えられた新しい薬の作り方を勉強しましょう。 -
153工学系情報工学デジタル画像の仕組みと画像処理工学部情報工学科
講師 上田 千晶講義近年はスマートフォンの操作だけで簡単に写真を撮影・保存・表示・さらには加工することができますが、内部では様々な処理が行われています。本講義ではデジタル画像の保存形式の違いや簡単な画像処理など、デジタル画像に関する基本的な知識や技術について解説します。
-
154工学系応用化学モノづくりを支える化学工学!応用化学科
教授 押谷 潤講義『化学工学』という言葉、高校までの授業ではあまり聞き慣れないと思いますが、実はこの化学工学、モノづくりにおいて非常に重要なんです!実験室でのフラスコなどを使った基礎研究の成果を、実際の化学製品の生産に役立てる、それが化学工学の使命です。製品生産に欠かせない反応を取り扱う化学だけでなく、物理も関連します。と言いますのも、化学製品を生産する工場では、原料の加熱や粉砕、生成物の冷却や分離など、物理が関連する様々な操作も必要なので、それらも化学工学の一部というわけです。本講義では、化学工学がどういうものなのかを分かりやすくご紹介したく思います。