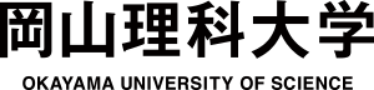-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
224理学系生物学ハキリアリと話す方法について動物学科
教授 村上 貴弘講義動物と話せるようになるのは非常に魅力的です。もちろん子どもの夢のような話としても面白いのですが、動物社会学や言語学としても非常に興味深いテーマです。現在、人間以外で言語を持っていると正式に証明されているのはシジュウカラだけですが、岡山理科大学ではハキリアリの研究を進めることで、アリも言葉を話せるのではないかと一生懸命検証しています。アリは何を喋っているのか?どのような役割があるのか?果たして言葉は社会にとってどのような影響を与えるのか?一緒に考えてみましょう。
-
225理学系生物学メンデルの法則と「サイエンス」動物学科
講師 布目 三夫講義グレゴール・ヨハン・メンデルが1866年に発表した「遺伝の法則」は皆さん知っていると思います。ただ、彼がどのような着眼点・実験的手法で、その法則を見出したか、ご存知でしょうか。メンデルが行った手法は、現在の研究者が基本的に扱っている「サイエンス」的な手法でしたが,150年前の研究者には馴染みのない革新的なものだったのです。それが、「遺伝の法則」が論文として発表されてから世界が認めるまでに、長年月が必要だった要因の一つと考えられています。この講義では、メンデルの実験を通して、「サイエンス」的な考え方の基本を知ってほしいと思います。
-
226理学系生物学動物の冬眠戦略 ~飢えと厳冬を乗り切る~動物学科
教授 水野 信哉講義動物の共通祖先は南方で発生、種分化を繰り返してきた。やがて様々な動物種は北上し、御大から寒帯へとその生息地を拡げる事に成功してきた。この過程で、厳冬や飢餓を克服すべく、ある種の動物種は冬眠という戦略を獲得してきた。例えば、ヤマネは外気温である5℃にまで体温を落とし、心拍数や呼吸数も激減させ、生命活動に必要な最低限のレベルにまで代謝を落とす事により飢餓を克服できる。講義では、このような冬眠戦略の醍醐味、厳しい寒さの克服に向けた代謝機構について、最近の知見を交え、紹介したい。
-
227工学系機械工学くらしを支える流体力学機械システム工学科
准教授 岩野 耕治講義流体力学は、空気や水の動きを解き明かし、工学や環境問題の解決に役立つ学問です。私たちが普段使っている電気も、その多くが流体の力を利用して作られています。例えば、火力発電や原子力発電では、高温の蒸気でタービンを回し、風力発電では風の力で羽根(ブレード)を動かし、水力発電では川やダムの水の流れでタービンを回します。このように、流体の動きをうまくコントロールすることは、エネルギーを効率よく生み出すために欠かせません。さらに、この流体力学は自動車や飛行機の設計にも活用され、空気の流れを調整することで燃費を向上させたり、飛行機がスムーズに飛べるようにしたりしています。また、台風や線状降水帯による大雨などの自然災害を予測し、防ぐためにも流体の研究はとても重要です。本講義では、このように私たちの生活と深く関わる流体力学について、わかりやすく説明します。
-
228工学系機械工学貨幣の作り方から「ものづくり」を学ぶ機械システム工学科
准教授 寺野 元規講義自動車や飛行機,身の回りの製品の作り方を考えたことはありますか?貨幣(お金)と自動車などの部品の製造方法は同じ技術です.特に日本の貨幣は諸外国よりも精巧であり,日本の「ものづくり」技術の高さがうかがえます.この講義では,貨幣の変遷・作り方を通して,現在の日本を支える「ものづくり」を説明します.
-
229理学系生物学・地球科学モンゴル恐竜学入門恐竜学科
教授 實吉 玄貴・藤田 将人・加藤 敬史・髙橋 亮雄・辻極 秀次
准教授 林 昭次講義近年、恐竜研究は世界各地のみならず日本においても活発に行われるようになり、恐竜類の種の多様性、生理、生態、そして当時の環境に関する新たな知見が次々と明らかになってきました。本講義では、岡山理科大学がモンゴル・ゴビ砂漠を主なフィールドとして展開している恐竜学の最前線の研究や発掘活動の成果を紹介するとともに、それらを活用した大学での教育の取り組みについても解説します。恐竜を手がかりに、過去の地球環境や生命の進化に迫る学びの魅力を体感してください。
-
230理学系生物学・地球科学化石から探る琉球列島のふしぎな動物相の起源恐竜学科
教授 髙橋 亮雄講義九州と台湾の間に弧状に連なる琉球列島には、日本本土とは趣を異にする多様な動物が分布しているだけでなく、ハブのなかまやリュウキュウヤマガメ、アマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコなど、この地域にしか見られない固有種が多く含まれていることでもよく知られています。さらに、ほんの数万年前の地層からは、リュウキュウジカやオオヤマリクガメといった絶滅種が多数発見されており、比較的最近まで、豊かで独特な動物相がこの地域に存在していたことが明らかになってきました。本講義では、こうした琉球列島の動物相に着目し、現生生物の分布パターンに加え、化石記録や地質学的データを手がかりに、この地域の古地理の変遷と、それにともなう動物の起源、種分化、絶滅の背景について、最新の研究成果をもとに解説します。地質・古生物と生物の両面から琉球列島の成り立ちに迫る、進化と環境変動のダイナミズムを学んでみませんか?
-
231理学系生物学・地球科学恐竜から探る脊椎動物の巨大化の限界恐竜学科
准教授 林 昭次講義私たちの地球には、かつて体長30メートルを超える巨大な陸上動物が存在していました。それが、竜脚類と呼ばれる恐竜たちです。彼らは現在のクジラに匹敵するほどの大きさにまで成長し、脊椎動物の進化史上、最大の陸上動物として知られています。しかし、なぜ竜脚類だけがこれほどの巨大化を遂げることができたのでしょうか?そして、なぜ哺乳類やその他の脊椎動物は、同じような進化を遂げなかったのでしょうか? この講義では、骨の構造や呼吸器系、成長速度といった解剖学的特徴に注目し、竜脚類の体に隠された“巨大化の秘密”を解き明かします。また、哺乳類との比較を通じて、脊椎動物が進化の過程で直面した「巨大化の限界」に迫ります。
-
232理学系生物学・地球科学骨の多様な役割と生物の進化恐竜学科
教授 辻極秀次講義骨は体を支え、脳や肺などの臓器を守るだけでなく、耳小骨として音を伝えたり、カルシウムを貯蔵したり、血液を作ったりと多様な役割を持っています。哺乳類は、進化の過程で、顎の骨を耳小骨に変化させることにより聴力を大幅に増大させ、厳しい生存競争を勝ち抜きました。カルシウム貯蔵器官としての骨は、血液の凝固,筋の収縮や神経系の機能など生命の維持に重要な役割を担っています。また、鳥類や一部の恐竜では,骨髄骨とよばれる骨が卵の殻を作るのに用いられています。哺乳類では骨で血液を作りますが、カエルでは脾臓・肝臓・腎臓でも作ります。
本講義では、このような骨の構造や多彩な機能など、骨を構成する細胞や組織に着目して、ヒトなどの哺乳類や他の生物と比較することにより生物進化に迫ります。 -
233理学系生物学・地球科学小さな化石から分かること恐竜学科
教授 加藤敬史講義日本の哺乳類化石は、おもにゾウやシカといった大型のものの研究が中心に行われてきましたが、近年、小型の哺乳類を古い時代の地層から抽出することが可能になって、日本の哺乳類相の変遷と東アジアの哺乳類の適応放散の歴史が少しずつ明らかになってきています。本講義では、探索的な化石調査の手法と研究の実例を紹介し、小型の哺乳類化石をつかって生物相の変化を理解する手法を学びます。
-
234教育学芸術教育音楽と美術でアート脳をみがこう初等教育学科
教授 妻藤 純子
准教授 井本 美穂講義いま、ものの見方を拡げたり、生活を豊かにしたりするひとつの方法として、アートが注目されています。
一緒に音楽と美術でアートの力を感じませんか?
【探究活動をサポートします。】 -
235教育学スポーツ教育楽しもう「創るスポーツ!」初等教育学科
准教授 北原 和明講義実験「する・みる・支える・知る」に続く第5のスポーツ「創るスポーツ」。いつでも・どこでも・誰とでも楽しめるスポーツを皆で創ってみませんか!
【探究活動をサポートします。】 -
236教育学教育制度・教育史「教育」とは何か?初等教育学科
准教授 土井 貴子講義これまでたくさん「教育」を受けてきましたね。「教育」と聞いて何をイメージしますか?みなさんの経験から学校教育を連想するかもしれませんね。
「教育」という営みは、いつの時代も、どの地域でも同じなのでしょうか。そうではないですね。
教育学に関心のあるみなさんと「教育」とは何かを考えてみたいと思います。
【探究活動をサポートします。】 -
237教育学教育心理学やる気を出すにはどうするか?モチベーションの心理学初等教育学科
准教授 奥村 弥生講義勉強のやる気を出すためにはどうすればよいのでしょうか?心理学において、やる気は「モチベーション」や「動機づけ」と呼ばれ、様々な研究が行われています。
モチベーションの高め方には人によって違いがあります。あなたのモチベーションの傾向を知るためのワークに取り組んでみましょう。
モチベーションの知識を身に着け、自分自身の勉強に生かしたり、身近な人のモチベーションを高める工夫につなげたりしてもらえたらと思います。
【探究活動をサポートします。】 -
238教育学家庭科教育人は「見た目」が○○%!?初等教育学科
准教授 原田 省吾講義「人を『見た目』で判断してはいけない!」とよく言われますが、そもそも「見た目」とは何なのでしょうか?
人を「見た目」で判断すること何か大変なことが起きるのでしょうか?
そんな「見た目」について、これまでの家庭科の学習を活用しながら一緒に追究していきましょう!
【探究活動をサポートします。】 -
239教育学教育社会学日本の家族はこれからどうなる?-近現代史から未来を考えよう初等教育学科
教授 松岡 律講義皆さんが日常当たり前に接している家族の姿。実はこれ、そんなに昔からある姿じゃないんです。
例えば「親に口ごたえする」なんて、今の90代以上の人にとってはほぼ不可能な時期もあったんです。
日本の家族は、いつ頃から今のようになり、この先どうなって行くんでしょう。
一緒に考えてみませんか?
【探究活動をサポートします。】 -
240教育学教育学国際バカロレア(IB)教育・IB教員資格はなぜ日本の国策?そもそも「日本」って何?教育学部
中等教育学科
教授 ダッタ シャミ講義海外で生まれ、どこの国にも属さない、国際バカロレア(IB)教育はなぜ日本の国策なのか?そのIB教員資格はなぜIB校以外の日本の学校でも重宝されるのか? そもそも「日本」って何?「日本人」って誰? 「私」は誰? 国、地域、文化、個人の「identity」をあなたはどう捉えるか? それらのidentity形成に教育はどう関わるのか? これらの問いについて、多角的・多面的に一緒に考えましょう。
【探究活動をサポートします。】 -
241教育学教育学日本人が書き残した漢詩文~漢文とは、日本語であった!?~教育学部
中等教育学科
准教授 奥野 新太郎講義漢文って、外国のものだとばかり思っていませんか?なぜ日本の学校では中国の言葉である漢文を勉強するのでしょうか?その答えの一つは、日本という国の言葉の歴史にあります。昔の日本人は、漢文を読み書きに使っていました。実はマルチリンガルだった昔の日本。漢文とは、私たちの祖先が書き残したものを受け継ぐための「魔法の鍵」なのです。そんな日本の漢文の世界を、皆さんにご紹介しましょう。これでもう、「漢文なんて自分には関係のないもの」だなんて思わないはず!
-
242教育学教育学批判的な思考とは?教育学部
中等教育学科
教授 福島 浩介 又は、教授 ダッタ シャミ講義批判的な思考とはどんなものをいうのでしょうか。国際バカロレアで高校2・3年生が履修する「知の理論(TOK、Theory of Knowledge)」という科目があります。この科目では、「知識の本質とはなにか」ついて考えるのですが、そのなかで「批判的な思考を培う」ことも行われます。実際には二年間で百時間ほどの授業を行うのですが、その一端をご紹介します。
【探究活動をサポートします。】 -
243教育学教育学探究、どうでしょう?教育学部
中等教育学科
教授 福島 浩介 又は、教授 ダッタ シャミ講義高等学校では「総合的な探究」という時間があり、生徒諸君一人一人が「探究」という学び方を身に付けることを必要とされます。では「探究」という学び方とはどんなものなのでしょうか、初歩の初歩のお話をし、「探究」を「探究」してみたいと思います。
【探究活動をサポートします。】