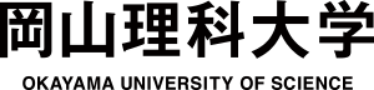-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
175工学系建築学ZEBについて建築学科
教授 坂本 和彦講義ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)とは、建築物における一次エネルギー消費量を、建築物・設備の省エネ性能の向上や、オンサイトでの再生可能エネルギーの活用等 により削減し、年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロまたは 概ねゼロとなる建築物のことをいいます。このZEBの考え方や諸技術について解説します。
-
176工学系建築学建築の空間について建築学科
教授 増田 俊哉講義建築の空間とはどういったものなのか、その空間を人はどのようにして感じることができるのかを手始めに解説します。そして、その建築空間を快適に感じるための手法について設計の観点より、歴史的な事例から近現代の事例をもとに解説します。
-
177工学系建築学建築基礎と地盤について建築学科
教授 堀田 洋之講義建築物は基礎と呼ばれる構造を介して地盤に支えられています。建物の建つ地盤の種類や性質に応じて、基礎は様々な形態を取ります。地盤の特徴的な性質をいくつか説明し、基礎の計画・設計方法について解説します。
-
184獣医系獣医学動物のもしものときの応急手当獣医学科
助教 大西 章弘講義今、動物を飼育している人も飼育していない人もどこかでケガをした、または病気の動物と出会うかもしれません.そのときにどうしたらいいかはきっとその場では慌ててしまうでしょう.少しだけ落ち着いてそのときに対応できるように簡単な応急手当を心に留めておけるようにしましょう.
また飼い主が見当たらない犬、猫、野鳥に出会ったときにどうしたらよいのかも一緒に少しだけ覚えていきましょう. -
185獣医系獣医学分子から見る筋肉の収縮獣医学科
講師 竹谷 浩介講義私たちが体を動かすとき筋肉が収縮、もしくは弛緩します。このとき筋肉細胞の中では様々な分子が協同して働いています。例えば、筋肉が収縮するときには力を発生するモーターの役割を果たすミオシンと呼ばれるたんぱく質分子は高エネルギー分子であるATPを消費し、アクチン分子からなるレールの上を一定方向に移動します。この講義では筋肉の収縮の仕組みを分子レベルで考え、生命現象を分子レベルで考えるきっかけにしていただきたいと思います。
-
187獣医系生理学微小-リンパ循環の理解から
Bench to BedsideとBedside to Benchを考える獣医学科
教授 水野 理介講義
多くの無脊椎動物では循環系は開放血管系で、血液は細胞間隙を直接流れている。完全な閉鎖血管系は魚類に至って初めて起こり、末梢血管抵抗が増すため血圧も高くなる。全身の血圧調節は、抵抗血管である細動脈の収縮-拡張によって直接制御される。毛細血管床・細静脈は、物質交換や免疫担当細胞の移動路として機能する。毛細血管床と細動脈、細静脈を一括して微小血管系と呼ぶ。この微小血管系、組織間隙とリンパ系を含めて微小循環とされる。血液循環の主目的が生体内部環境の維持、すなわち全身の各組織細胞に対する生活物質供給と代謝産物除去にあることを考えるなら、微小循環こそまさに循環系で最も本質的なメインプレイヤーである。全身の細胞の生活条件は微小循環によって直接規定される。微小循環の障害は当該組織の機能不全を引き起こし、障害の部位と広さによって生命の喪失につながる。この意味において、微小循環の世界は、その名称から想像されるような微小な存在ではなく、細胞の個々からその統合体としての個体の生命維持を直接左右する巨大なシステムであることを解説します。 -
188獣医系獣医学血管の欠陥獣医学科
教授 江藤 真澄講義身体中に酸素や栄養素を届け、排気ガスや不要物を回収する為に張り巡らされている血管は人を含めた動物が持つもっとも巨大な臓器です。また、血管はただの管ではなく、神経やホルモンなどの刺激に応じて収縮・弛緩を繰り返すことで心拍からの血流に抵抗するとともに物質を末梢で交換するために必要な圧力を維持しています。本講義では講師が日本とアメリカにて行ってきた血管の運動性に関する研究のエピソードを交ぜながら、筋肉としての血管について皆さんと一緒に考えたいと思います。
-
189獣医系獣医学・生物学いろいろな解剖学とその役割獣医学科
教授 松井 利康講義解剖学は、獣医師も含めて医療者を目指す学生が、専門科目として最初に受ける講義の1つです。病気やその治療の組み立ては、動物やヒトの体の構造と機能を学ぶことで,はじめて理解できるようになります。講義では、体の構造が病気などと関連する具体例を示しながら,病理解剖・法医解剖など様々な解剖が医学分野で担っている役割を紹介します。
-
191獣医系公衆衛生学・予防医学地震による健康被害とその対策獣医学科
教授 神林 康弘講義地震による健康被害には生き埋めなどの直接的被害とPTSDをはじめとした精神的被害などの間接的被害があります。地震による健康被害にはどのようなものがあるかをお話しするとともに、その対策について説明します。また、阪神大震災以降進んできたわが国の地震に対する対策について紹介します。我々が行なった能登半島地震による高齢者の健康被害に関する調査研究も紹介します。
-
192獣医系公衆衛生学・環境医学黄砂や微小粒子状物質(PM2.5)などの大気粉塵による健康影響
ー大気粉塵中化学物質と呼吸器アレルギー疾患-獣医学科
教授 神林 康弘講義黄砂や微小粒子状物質(PM2.5)などの大気粉塵が大陸から偏西風により運ばれてくる越境汚染が問題になっています。また、国内の幹線道路などでもPM2.5は発生します。このような大気粉塵による健康被害が懸念されています。大気粉塵による健康被害にはどのようなものがあるか、どのような物質が関連しているかお話しします。PM2.5は、中国で高濃度になっているということで一般に知られるようになりました。中国だけでなく、インド、ベトナム、インドネシアなどでもその濃度は中国と同レベルとなっています。世界における大気汚染の状況やモニタリングについても触れます。捕集した大気粉塵中化学物質と慢性咳嗽(アトピー咳、咳喘息、気管支喘息)患者の症状との関連に関する我々の研究も紹介します。
-
193獣医系公衆衛生学・予防医学ヒトを対象として疾患の要因を調べるには?
-疫学研究、特に、コホート研究について-獣医学科
教授 神林 康弘講義ヒトの疾患とその要因を調べる研究に疫学があります。疫学では、ヒトの疾患とその要因を明らかにするだけでなく、健康状態を改善(予防)する介入も行います。疫学にはどのような研究デザインがあるか、特に、住民を対象として長期にわたり追跡することにより(曝露)要因と疾患(健康影響)の関連を明らかにするコホート研究について、代表的な久山町研究やフラミンガムハートスタディーにも触れながらお話しします。我々が石川県能登の志賀町で全住民を対象として行なっている調査研究も紹介します。
-
194獣医系化学・生化学酸化ストレスと疾患獣医学科
教授 神林 康弘講義酸化ストレスは種々の疾患に関連すると考えられています。酸化ストレスを引き起こす分子(活性酸素種やフリーラジカル)にはどのようなものがあるか?酸化ストレスにはどのような反応が関与しているか?酸化ストレスを防御する機構にはどのようなものがあるか?酸化ストレスのバイオマーカーにはどのようなものがあるか?研究成果にも触れながら、酸化ストレスと疾患に関する基本的事項をご紹介します。
-
196獣医系獣医保健看護学人と動物の健康-動物由来感染症を学ぶー獣医保健看護学科
教授 小野 文子講義動物から人に感染する病気「動物由来感染症」は自然環境の変化や社会の多様化に伴った対応が必要となります。最新の知識を学んで、人と動物が健康で幸せな生活を送るために大切なことを一緒に考えましょう。
-
197獣医系獣医保健看護学イヌと過ごす健康ライフ -人と動物の健康づくり-獣医保健看護学科
教授 古本 佳代講義イヌと一緒に暮らすことで、”こころ”も”からだ”も健康になることを知っていますか?イヌとのふれあいや散歩は、ストレスの軽減や運動不足の解消に役立ち、健康づくりに大きな効果があります。この講義では、イヌと人の健康的な関係について、科学的な視点からわかりやすく解説します。イヌと共に暮らす楽しさや、地域社会とのつながりについても考えてみましょう。
-
198獣医系獣医保健看護学人々の食生活を豊かにする畜産を守れ! タケノコ獣医師が想うこと獣医学科
准教授 久枝 啓一講義日本の国土面積は小さくて山地が多いため、食料生産の効率が悪い国土となっています。そんな中、畜産産業は、地域を選ばず効率よく畜産物を生産し、日本の農業に収益面で大きな潤いを与えてきました。また、国民の食生活を豊かにしてきました。ところが、昨今のコロナ禍で世の中の経済が停滞する中、自粛ムードにより牛乳や牛肉の消費が大きく落ち込み、畜産農家が採算の取れない経営状態になっています。このような時こそ私は本学科で学んだ若い人たちが、知恵と工夫を用いて未来の畜産に希望が見いだせる人材になってほしいと思っています。私は32年間畜産の現場で臨床獣医師として勤務し、多くの失敗をしてきました。その経験から畜産の現場に携わる人材がいかにあるべきかをお話しします。
-
199獣医系動物看護学高齢動物と看護獣医保健看護学科
准教授 佐伯 香織講義ヒトの高齢化と同様に動物も高齢化が進んでいます。高齢期を迎えると性格的・行動的変化や身体的変化がみられ、日常的なケアを必要とすることが多くなります。ここでは、加齢に伴う動物の体の変化を理解し、健康維持のためにどのようなケアが必要かお話します。
-
200獣医系実験動物学動物のストレスを測る獣医保健看護学科
講師 野原 正勝講義みなさんもストレスを感じることがあると思いますが、ストレスの度合いを数値で見たことはありますか?みなさんがストレスを感じるのと同じように、動物もストレスを感じることができます。この講義では、動物が感じているストレスを測定する(数値化する)研究についてお話します。
-
201獣医系獣医保健看護学動物との正しい接し方獣医保健看護学科
講師 宮部 真裕講義多くの動物病院には日々様々な種類や性格の動物が来院します。そんな動物には接し方を間違えると診察をする上でとても嫌がるようになってしまうような性格の動物もいます。普段動物と接することが少ない人も、正しい動物との接し方について考えてみましょう。
-
202獣医系汎動物学・実験病理学ズービキティ研究の可能性:動物から人の病気を理解する獣医保健看護学科
教授 木村 展之講義ヒトと動物には様々な共通点がありますが、その中には病気も含まれます。例えば、ヒトと同じようにイヌも高齢になると認知症を発症することがあります。そこで、ヒトと動物は同じ生き物(動物)であるという考えのもと、病気も一緒に診て・考えていこうというズービキティ(汎動物学)が生まれました。ヒトに近縁な霊長類を用いたアルツハイマー病研究の成果を中心に、ズービキティ研究の可能性についてお話ししたいと思います。
-
203獣医系動物福祉学動物福祉について獣医保健看護学科
教授 木村 展之講義最近は動物愛護や動物保護に関する情報が様々なメディアで大きくとりあげられるようになりましたが、動物福祉という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
海外では当たり前になりつつある動物福祉という考え方について紹介するとともに、私たち人間の生活を支えてくれている動物たちの幸せについて考えてみましょう。