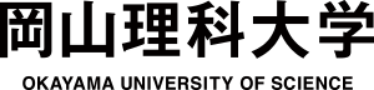-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
27人文・社会科学系法政・社会学人権とは何か-世界と日本、差別をなくすには獣医保健看護学科
講師 戸田 修司講義日本国憲法は、基本的人権を原則としています。では、どうして日々メディアで取り上げられるパワハラ、セクハラ、いじめがなくならないのでしょうか。この授業では、人権の成立過程をたどりながら、人権の本質についてお話しします。また、日本の人権状況は世界標準から見てどのように評価すればよいのかを一緒に考えます。
-
31情報系情報科学高性能計算機を活用したビッグデータ分析とその応用情報理工学科
教授 李 天鎬講義多種多様なデータが日々大量に生成されています。何らかの目的を達成するためには、それら大量のデータを分析し有用な知見を見いだす必要があります。超高速な大規模計算を可能とする高性能計算機(スーパーコンピュータ)やAI・機械学習モデルのお話と、それらを活用したビッグデータ分析とその応用事例について紹介します。
-
32情報系情報科学人工知能とゲーム情報理工学科
講師 秋山 英久講義我々の日常生活でも利用されるようになってきた人工知能技術は,ゲームの世界でも活躍しています.特に,囲碁・将棋などに代表されるボードゲームは,人工知能技術を競う目的で古くから利用されてきました.近年は,ビデオゲームにおいても人工知能技術が重要な要素となってきています.ゲームにおける人工知能技術について,歴史的な側面も交えながら解説をします.
-
33情報系情報科学深層学習による画像・自然言語生成情報理工学科
教授 椎名 広光講義ニューラルネットの組合せを深層化することにより人工知能の適用分野が広がってきています。認識だけではなく生成ができるようになっています。人工知能による生成の中でも画像や自然言語に関する内容を解説します。
-
34情報系情報科学数値解析入門(コンピュータで計算する)情報理工学科
教授 河野 敏行講義数学の授業で、紙と鉛筆で計算する仕方はしっかり習っているでしょう。しかし、難しい問題になると手で計算するのは大変ですよね。コンピュータで計算させることはできますか? コンピュータで計算するためのテクニックや注意などを紹介したいと思います。
エクセルが使える環境であれば,エクセルを用いた数値解析の実習をします. -
35情報系情報科学デジタルメディアとコンピュータゲーム情報理工学科
講師 菅野 幸夫講義メディアの発達は人間の暮らしを大きく変えてきました。グーテンベルクによる活版印刷の発明、1960年代に起きた電話、映画、TV等、電子メディアの急激な発達、そして今、デジタルメディアがわたしたちの生活に大きな影響を与えています。
デジタルメディア(動画投稿サイト、SNS、音楽配信、アニメ、etc.)の社会への影響力・可能性についてコンピュータゲームを軸にしてお話します。 -
36情報系情報科学グーグル検索の数理- PageRank とは -基盤教育センター
教授 中川 重和講義検索サイト グーグル で用いられているホームページのランク付けの原理は PageRank と呼ばれています. PageRank についての数理的な側面を平易に解説します.
-
37情報系情報科学ビッグデータと可視化情報理工学科
准教授 廣田 雅春講義現在、TwitterやInstagramなどのソーシャルメディアに対して、テキストや写真などのコンテンツが大量に投稿されています。このようなデータは、ビッグデータと呼ばれ、多種多様な情報が含まれています。そのビッグデータに含まれる情報を分析する技術や可視化する技術について解説します。
-
38情報系情報科学コンピュータプログラミングの基礎フロンティア理工学研究所
教授 畠山 唯達講義実験プログラミングと聞くとかなり複雑でとっつきにくいと思われがちですが、実際はきわめて合理的でルールに則った手続きを行う実践の場です。現在では、コンパイラ等を導入しなくてもすぐに使えるプログラミング環境や、ウェブで試すことができる環境なども普及しており、以前と比べてその敷居は低くなっているでしょう。本講義では「Scratch(MITメディアラボが開発した初心者向けプログラミング環境)」を利用して、プログラミングでできることの基礎、簡単な考え方、さらに「自分の頭の中の考えをバラバラにしてコンピュータに命令する」と言う体験をしていただきたいと考えております。
(本授業は実習形式のため、学校等のコンピュータ室で児童生徒が利用できるPC環境(ブラウザを利用してネットにつなぐことができること)を用意していただけることを前提としております。詳細はお問い合わせください。)
※ 2023年度注意:小学校~高等学校の教育課程が変更になり、プログラミングに関する授業が必修化しました。本授業はその内容と大きく重複する可能性があります。従いまして、「プログラミング教育を受けていない年次」を対象とさせていただきます。プログラミング既修者向けに別途「自然科学でコンピュータプログラムはどのように使われているか」を用意しております。 -
39情報系情報科学・理学全般自然科学でコンピュータプログラムはどのように使われているかフロンティア理工学研究所
教授 畠山 唯達講義実験コンピュータプログラムと聞くと、多くの人はゲームやスマートフォンのアプリなどを想像するのではないでしょうか。しかし、プログラム(=コンピュータによる計算)は我々の生活も関連する様々な分野で様々な使われ方をしています。中でも自然科学(理学)の分野では、大きく分けて「シミュレーション」と「データ解析」と言う2つの用途で使われ、科学の発展に大きく寄与してきました。本講義では現在コンピュータプログラムが使われている事例をいくつか紹介し、コンピュータが科学にいかに貢献しているかをご説明します。また、生徒さんがプログラミング環境をお持ちで実習ができる場合は、「シミュレーション」と「データ解析」の入り口を実習していただくことも可能です。
(実習形式の場合は、生徒が個々保持するPC・タブレットや学校等のコンピュータ室の環境を用意していただけることを前提としております。詳細はお問い合わせください。)
※ 2023年度注意:小学校~高等学校の教育課程が変更になり、プログラミングに関する授業が必修化しました(年次進行中)。本授業はその内容を既習である生徒向けのものです。 -
40情報系情報処理はじめて学ぶデータサイエンス経営学科
教授 森 裕一講義実験「データの活用」として学んでいる知識は現代人に必須のもの。しかし、単に、平均の算出やグラフの描画で終わっていませんか。場面に応じてどんなデータをとるか、それをどう処理をするか、出てきた結果から何を読み取るか、そして、それらを基にどう行動を起こすか、これら一連の流れが「データサイエンス」では大切です。この講義では、「データ」を活かして「科学」する具体的な方法や工夫を、実際のデータを処理しながら学びます。調査や課題研究でのデータの分析につながる「役に立つデータサイエンス」を体験しましょう。
※ExcelかRがインストールされた実習室での実習も可能です。 -
41情報系情報処理身近な話題でデータサイエンス経営学科
教授 黒田 正博講義新聞や雑誌にのっているデータやグラフの読み方、アンケート調査などで得られるデータから有用な情報をどうやって取り出すか、あるいはウソのデータをどうのようにして見分けるかなどを、身近の例題を使って講義します。
また、データ情報の視覚的な表現法やプレゼンテーション法などについても話します。 -
42情報系情報処理はじめて学ぶスポーツデータ分析経営学科
准教授 久永 啓講義サッカーや野球、バスケットボールといった各スポーツにおいて、チーム・選手の強化、スポーツ組織の成長、観戦満足度向上などのためにデータを活用する機会が増えてきています。この講義では、そのようなスポーツ現場で実際に行われているデータの取得や活用について、講師の現場経験や国内外の最新事例を用いた講義、擬似体験ワークなどを通じて学びます。
-
43情報系情報処理データリテラシーを身に付けよう経営学科
講師 藤原 美佳講義「数値データ」から、あなたは何を読み取ることができるでしょうか?
データリテラシーを身につけることで、「データ」を正しく読み取り、「数値」に隠された本質を見抜くことができます。この講義では、数値だけではわかりにくい「データ」を視覚的に表現することで、データの特徴を直観的に把握し、正しくデータを分析する方法について学びます。 -
44情報系情報処理はじめて学ぶデータ二次分析経営学科
講師 塚常 健太講義実験世の中では様々な人や機関が様々なデータを集めています。研究者自らが新たなアンケート調査を企画するだけでなく、既に存在するデータを使わせてもらって分析する、「二次分析」「二次利用」と呼ばれる研究もますます盛んになっています。この授業では世の中の調査とデータについての概要を解説した後、都道府県や市町村などのデータを用いた二次分析を体験します。
-
45情報系情報処理健康のために「からだ」のデータを測る経営学科
講師 石田 恭生講義豊かな人生を送るためには、健康づくりが重要です。「からだ」の中から、体重、体脂肪、心拍数、体温、血圧などを測ることで、健康維持に役立てている人も多いと思います。これらのデータの解説だけでなく、トレーニングや健康づくりをすることによって、どのように変化するのかをデータなどを通して、解説します。
-
46理学系数学一刀切りの数学応用数学科
教授 大江 貴司講義実験一刀切りとは、紙を折りたたんでハサミで一回だけ切ることにより、目的の図形を切りだすことを言います。正方形や星型なんかは簡単に切りだすことができますよね。
でも、それより複雑な形はどうでしょうか?
実は線分で構成される図形はどんな形でも一刀切りで切りだすことができます。この講義ではその方法を説明するとともに、紙とハサミを用いて実際に体験してもらおうと思います。
※その他(具体的に: 講義、および紙と定規、コンパス、ハサミを使った実習を行います。) -
47理学系数学整数と素数について応用数学科
教授 浜畑 芳紀講義整数は、…、-2、-1、0、1、2、…のように規則正しく並んでいます。整数を分解していくと、素数と呼ばれる「数の原子」が現れ、2、3、5、7、11、13、…のように不規則に並んでいます。これらの数には驚くべき不思議な性質が秘められています。講義では、整数や素数のもつ不思議な性質を紹介します。
-
48理学系数学曲面の分割とオイラーの定理とトポロジー応用数学科
教授 黒木 慎太郎講義多面体の頂点の数をV、辺の数をE、面の数をFとしたときに,V-E+F=2と言うオイラーの公式が知られています.これは球面を頂点と辺と面で分割しても同じ値になることが知られています.つまり,2という値は球面の性質だといえます.では他の曲面を頂点と辺と面に分割すると値はどうなるでしょうか?この講義では,その問に答えを出す形でトポロジーと呼ばれる数学の分野の入門を行います.
-
49理学系数学曲線の曲がり具合とは応用数学科
講師 井上 雅照講義道路で自転車などを運転しているとき、カーブを曲がりきれなかったことはありませんか。
円や直線などは均一に「曲がって」いますが、一般の曲線ではどうでしょうか。
パソコンを使って実習を行いながら、いろいろ考察していきます。
*実習を行う場合「Grapes」をインストールしてあるパソコンが必要です。