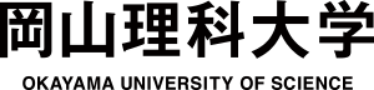-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
94理学系生物学動物の生殖と脳動物学科
准教授 託見 健講義ヒトを含む動物には寿命がありますが、子供を産み、育てることで寿命を越えて同じ種の個体を後世に残すことができます。このように同種の新しい個体を生み出すことを生殖と呼び、哺乳動物の生殖を調節しているのはホルモンです。そして、ホルモンを調節しているのは脳です。生殖に関わるホルモンの調節、また動物の一生の中でのホルモン分泌の変化について脳の働きと結びつけて解説します。
-
95理学系生物学オオコウモリに学ぶ生物学動物学科
准教授 中本 敦講義亜熱帯の森である沖縄のやんばるに棲むオオコウモリの暮らしぶりを題材にして、いろいろな視点から生き物を見るための観察力を養います。コウモリ類は日本の哺乳類の3分の1を占める繁栄したグループであり、日常でも姿を見かける身近な存在であるにもかかわらず、その姿はとても奇妙であり、その暮らしぶりは謎に満ちています。この授業では、日本本土ではあまり馴染みのない沖縄のフルーツ・バットを題材に、生き物の姿・形の意味、動物と植物の共進化、生態系における役割などを通して生物学のおもしろさを感じてもらいます。
-
96理学系生物学食べ物の来た道基盤教育センター
准教授 那須 浩郎講義お米,パン,野菜,果物など,わたしたちが普段食べている作物のほとんどが栽培植物です.これらの栽培植物は,もともとは野生植物でしたが,人が1万年の歴史の中で世界各地で改良してできたものです.私たちの食生活に欠かせない栽培植物が,いつ,どこで,どのようにして生まれ,いつ頃日本にやってきたのかをわかりやすく解説します.
-
97理学系生命科学・シミュレーションコンピュータシミュレーションで見るタンパク質の世界基盤教育センター
教授 矢城陽一朗講義コンピュータシミュレーションは他の方法では困難な問題の解決や予測を可能とし,また,物理学,数学,化学,生物学,生命科学など異分野の学問や研究を結びつけることができる重要な研究手法です.近年,スーパーコンピュータ「京」や「富岳」に代表される先端科学技術の革新により,コンピュータシミュレーションによる新しい創薬やものづくりが大きく変貌しています.本講義では,タンパク質の構造変化や,タンパク質が有機化合物(薬剤)とどのような相互作用をもち活性を示すのかをコンピュータシミュレーションの観点から解説します.
-
98理学系環境科学偏光顕微鏡で見る岩石・鉱物の世界基盤教育センター
准教授 佐藤 友彦
教授 青木 一勝講義実験偏光顕微鏡は、岩石の組織や構成鉱物の種類を調べるための特別な顕微鏡で、岩石学の研究にはなくてはならないものです。しかしそれ以上に、この顕微鏡で見る岩石・鉱物の世界は大変鮮やかで美しい世界です。この講義では、偏光板を使った簡単な実験と実際に岩石薄片を偏光顕微鏡で観察して、その美しい世界を体験することができます。
-
99理学系生命科学遺伝子って、なに?生物科学科
教授 池田 正五講義「遺伝子とは、なにか?」をわかってもらうために、まずその構造やはたらきについて、高校生がこれまで習ってきた知識でも理解できるようにやさしく説明します。さらに、それをもとに最近解き明かされたヒトのゲノムや遺伝子バイオテクノロジーについて、またそれらを利用した未来の産業・医療についてわかりやすく紹介します。
-
100理学系生命科学細胞が織り成す生命現象生物科学科
教授 南 善子講義生命の最小単位とも言える細胞は、活発に活動し、その形も中身も常に変化します。細胞の中では、小さな小胞や細胞小器官が活発に動き回り、生命の営みが行われています。さらには、細胞そのものも動き回ります。細胞自身も、その細胞の中の分子もどのようにして動くのか、その仕組みを分子レベルでやさしく解説します。
-
101理学系生命科学(1)バイオテクノロジーで読む昔話
(2)遺伝子組換え作物は安全?危険?生物科学科
講師 猪口 雅彦講義(1)桃から桃太郎は生まれるか?桃太郎・花咲か爺さん・さるかに合戦の昔話の世界を実現しつつある(?)植物のバイオテクノロジーのお話をします。
(2)遺伝子組換え作物は危険か?その作出の原理から従来の育種法との比較、メリットとデメリットについてお話しします。 -
102理学系生命科学クロマチン構造から探る生命現象生物科学科
准教授 河野 真二講義私たちのからだを構成する細胞の核の中には、およそ2 mにもおよぶDNAが存在しています。この長大なDNAはクロマチンとよばれる構造を形成して、わずか体積100 fL(fL = 1x 10^-15 L)ほどの微小空間である核の中に収納されています。この講義では、クロマチン構造がどのように形成され、遺伝情報の発現やDNAの複製などの生命現象に関わっているのか簡単に説明します。また、クロマチン構造の破綻によって引き起こされる疾患についても解説します。
-
103理学系生命科学森林と人の健康生物科学科
教授 汪 達紘講義「森林浴」という言葉を聞いたことがありますか?森林浴が人の免疫機能、自律神経活動、ストレスホルモンなどにどのような影響を与えるのかについて近年の研究事例を示しながら分かりやすく説明します。
-
104理学系生命科学目に見えない生き物たち
─微生物の世界─医療技術学科
教授 片山 誠一講義肉眼で見えない生物を、微生物と呼びます。微生物は、36億年前の地球で発生し、それ以来地球の至る所で生存し続けています。科学者たちは微生物をどのようにして発見し、研究してきたか、その歴史を解説します。そして、現代における微生物とヒトとの関わり合いについて紹介することにより、微生物に関する理解を深めていきます。高校生にも理解しやすいように画像をたくさん用いて説明したいと思います。講義の最後に高校生自分自身で指を培地にスタンプしてもらい、自宅で培養してもらいます。2、3日後には、自分と一緒に生きてきた細菌・真菌のコロニーが見られます。
-
105農・医療・生活科学系生命科学組織培養110年、再生医療への挑戦医療技術学科
教授 片岡 健講義動物細胞をシャーレの中で育てる「組織培養」の歴史は1907年、カエル神経細胞の培養からはじまりました。ちょうど100年目の2006年、京都大学の山中 伸弥教授が人工多能性幹(iPS)細胞の成果を発表し、2012年にはノーベル生理学・医学賞を受賞されました。この講義では組織培養学について概説するとともに、培養細胞の再生医療への応用と超えなくてはならないハードルについて紹介します。
-
108理学系生命科学植物の不思議な動き生物科学科
准教授 濱田 隆宏講義普段、私たちが気付かない植物個体の不思議な動きについて動画や模型を用いて紹介します。動画は小学生低学年から大人まで楽しめる内容です。学年や習熟度に合わせ、植物の動きを生み出す分子メカニズムについても説明します。またクイズ形式の参加型授業も可能です。動物と植物の違いや共通点を深く学ぶ機会を提供します。
-
109理学系生命科学小さな微生物の大きな力生物科学科
教授 三井 亮司講義微生物は病原性の悪者から、発酵食品やお酒、抗生物質の生産などの有用菌まで、とても身近な生物のはずですが、実際にはどこにいて、どんな形をして、どのようなのを食べているのだろうと考えてみると意外に知らないことが多いと思います。この講義では主に人に役立つ微生物を取り上げ、どのような場面でどのような微生物が活躍しているのか等を簡単に解説したいと思います。
-
110理学系生命科学化粧品のサイエンス生物科学科
教授 安藤 秀哉講義日光浴をするとなぜ日焼けがおこるのか、しみやしわはどうしてできてしまうのか、白髪や枝毛はどうやって生じるのか、皆さんは日ごろ疑問に感じたことはありませんか。化粧品には、ダメージを受けた皮フを健全な状態へと改善する作用があります。そして、そこにはさまざまなサイエンスがひそんでいるのです。
-
111理学系生命科学動物の体作りの仕組みを知る生物科学科
准教授 田所 竜介講義たった一つの受精卵からどうやって我々の複雑な体ができ上がるのでしょうか?これはまさに生命の神秘です。体作りの仕組みを解き明かすことは、再生医療や創薬などにも繋がります。この体作りの基本について、ニワトリ胚を題材として、一緒に易しく学びましょう。
-
112理学系生命科学恐竜のバイオメカニクス生物科学科
教授 内貴 猛講義太古の昔に地球を支配していたと思われている恐竜は、中には体重100トンにも達する巨大な恐竜がいたことが知られています。そんな恐竜を現在の地球によみがえらせたらどうなるだろうと考えたことはないでしょうか。でも、生体工学の立場から考えると現在の地球では巨大な恐竜は自分の体重を支えることができないのです。そのような話からはじめ、恐竜絶滅のなぞを考え、太古の地球に思いをはせながら、生物の大きさについて考えてみたいと思います。
-
113理学系地球科学電子スピン共鳴による第四紀年代測定と古環境変動古生物学・年代学研究センター
教授 豊田 新講義人類は、数百万年前から劇的な環境変動の中を生き抜き、現在の文明を築きあげてきました。そうした歴史、環境変動史の解明には、年代測定法はなくてはならない重要な科学的技術です。年代測定法を概観するとともに、その原理、実際の適用例、人類史における重要な問題点などについて講義します。
-
114理学系地球科学花こう岩のふしぎ生物地球学科
教授 能美 洋介講義実験地域の岩石や地層を題材に、岩石や日本列島や地殻の成り立ち、石材利用などについて講義します。
現地見学にも対応します。 -
115理学系地球科学身近な気象や大気環境を知ろう生物地球学科
教授 大橋 唯太講義実験身近な気象や大気環境が私たちの生活にどのように関わっているのかを解説します。また、気象の再現実験なども見てもらうことができます。