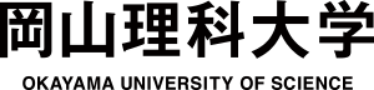-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
52理学系数学三山崩しを数学で情報理工学科
准教授 加瀬 遼一講義「3つの山にそれぞれ幾つかの石が置かれています。1つの山を選びそこから石を幾つかとっていきます。これを交互に繰り返し最後の石をとった方が勝ち。」これは三山崩しといういわゆる石取りゲームの一種です。
講義では三山崩しに隠された数学構造を解説し、このゲームを究めてもらいたいとおもいます。 -
53理学系数学15パズルの秘密基盤教育センター
准教授 小野 舞子講義15パズルとは、4×4のマス目に1から15の数字が書かれた15個のタイルを配置し、1マスの空所を利用してタイルを動かして遊ぶパズルです。左から右、上から下の順序で左上から右下にかけて、1から小さい順に15までのタイルを配置することができればパズルは完成です。
15パズルは、タイルの初期配置の状態によって完成することが可能であったり、不可能であったりします。この講義では、その理由を数学を用いて説明します。 -
54理学系数学代数方程式の歴史基礎理学科
教授 荒谷 督司講義1次方程式や2次方程式の解の公式は中学や高校で学びますが、3次方程式や4次方程式の解の公式については学びません。3次方程式や4次方程式の解の公式をめぐる興味深い歴史について紹介し、3次、4次方程式の解の公式を解説いたします。
-
55理学系数学数学を使ってあみだくじを自由自在につくろう基礎理学科
教授 荒谷 督司講義何かを決めるときに『あみだくじ』で決めることがあると思います。『置換』という数学の概念を用いると好きなようにあみだくじをつくることができるようになります。また、その際に一体年本の横線を引けばいいのかも計算で求めることができます。これらのことについて紹介いたします。
-
56理学系数学1+1=10 は正しいか?基盤教育センター
教授 大熊 一正講義数を数えたり,計算を行う際,我々は,通常,10進数を利用しています.しかしながら,我々の生活には,2進数であったり,12進数であったり,60進数であったりと,様々な進数が利用されています.そこで,様々な進数の利用場面を紹介しつつ,数値の意味について,再考してみましょう.
-
57理学系物理学放射線による被曝線量の計算と人体への影響古生物学・年代学研究センター
教授 豊田 新講義東北関東大震災で被害を受けた福島第一原子力発電所の事故によって、放射性核種が各地へ飛散し、周辺の放射線量が高くなりました。TVなどで飛散した放射線量について報道されましたが、一般の方には、いったいどれだけ人体に影響があるのか分かりにくかったと思われます。この講義では、放射性同位元素の解説から始め、自然放射線について、そして被曝線量の概念について講義します。外部被曝と内部被曝とに分けて、公表されている数値から被曝線量を計算する方法、そして、その人体への影響について解説します。
-
58理学系物理学シュレーディンガーの猫とタイムマシーン
~未来が過去を塗り替える!?~物理学科
教授 山本 薫講義実験微小世界の粒子は粒といっても常に揺らめいています。その性質は、「シュレーディガー方程式」という波動の方程式でよく説明できるのですが、この理論によれば、万物の運命さえも揺らめいて、箱詰めにした猫の命は生と死が重なり合って、中を覗くまで決まらない、というのです。本当でしょうか?未来が過去を塗り替える量子光学実験で、この不思議な世界を体験しましょう。
-
59理学系物理学物性物理の多彩な世界
~身の回りの磁石から量子コンピュータまで~基盤教育センター
准教授 稲垣 祐次講義物質の性質のほとんどは物質内に含まれる多くの電子の協力・競合現象の結果として生じています。普段何気なく使っているスマートフォン、その内部では電子が置かれた環境に応じて忙しく働いており、結果として我々は便利な機能を享受できています。
そういったデバイス等への応用の基礎となっている物質の物理的な性質を探求するのが物性物理学であり、中でも特に面白いのが低温における物性です。低温の世界では普段は全く意識することのない「量子性」と呼ばれる不思議な性質が物性を支配するようになり、奇妙な電気的、磁気的性質などが出現します。超伝導はその体表的な例であり、最近、注目されている量子コンピュータでも「量子性」がキーワードになっています。
本講義では、そういった興味深い現象を具体例を上げて紹介しつつ、直観的な理解につながるような分かり易い解説を行います。 -
60理学系物理学超・冷たい世界を探検してみよう基盤教育センター・アクティブラーナーズコース
教授 重松 利信講義実験温度が下がるどんなこと起こるのか。
私たち生きている世界と-200度の世界とでは何が違うのでしょうか。それぞれを比べた演示実験を行います。さらにもっと冷たい世界ではどんなことが広がっているのかを、講義と実験を通して学びます。 -
61理学系物理学素粒子と宇宙の世界物理学科
准教授 長尾 桂子講義実験この世界の物質は、素粒子と呼ばれる非常に小さな粒子に分解することができると考えられています。では、宇宙のすべてが素粒子に分解できるのでしょうか?実は宇宙のほとんどは、我々の知っている素粒子では説明できない物質でできています。また、すでに知っている素粒子についても、わかっていないことがまだたくさんあります。宇宙と素粒子の世界と、その謎について紹介します。ご希望があれば、演示実験を行います。
https://www.dap.ous.ac.jp/~nagao/highschool.html -
62理学系物理学非接触給電
─電源ケーブルが無くなる時代─物理学科
教授 石田 弘樹講義情報通信は無線化が進み、身の周りにの通信ケーブルは無くなりつつあります。最後に残されたのでは、コンセントにつなぐ電源ケーブルです。物理で習う「電磁誘導」と「共鳴」という現象を組み合わせると無線で電力を送ることができます。駐車場に電気自動車を駐車するだけで勝手に充電がされる時代がやってきます。講義では、非接触給電の原理と応用例を紹介します。
-
63理学系物理学磁石のふしぎフロンティア理工学研究所
教授 畠山 唯達講義実験中高の理科では永久磁石に関する説明はほとんどありません。私たちの身近にたくさんあり普段から何気なく利用している磁石ですが、意外に知らない特徴・性質がたくさんあります。磁石の面白い特徴について、100円ショップで揃うような材料を用いた簡単な実験を交えてお話します。テーマ:「磁石はなぜつく?」、「磁石がつくものとつかないもの」、「火であぶると磁力が消える?」、「鉄鉱石=天然の強い磁石」、「電磁石と永久磁石」、「方位磁石はなぜ北を指す?」など。
-
64理学系物理学グラフェンの科学基礎理学科
准教授 田邉 洋一講義グラフェンという物質は炭素原子1個分の厚みという極めて薄い2次元シートながら、軽くて丈夫、金属のように電気や熱を良く流すことから、シリコンや貴金属に替わる新しい材料として注目されています。講義では、実際に原子1層の厚みを実際に目で見て体感してもらいながら、グラフェンが近い将来どのように使われるのか紹介します。
-
65理学系地球科学磁石としての地球と私たちフロンティア理工学研究所
教授 畠山 唯達講義地球は巨大な磁石です。磁石としての地球が持つ基本的な様相と磁石の起源、磁石であるためにもたらされる惑星地球の特徴などを、動画などをお見せしながら授業形式で行います。
具体的には、
・地球は大きな磁石
・方位磁針は真北を向かない!?
・磁石がひっくり返る(地球磁場逆転)
・太陽+地球磁場+大気=オーロラ
・磁場を感じる生物たち
と言った内容を授業時間に応じて扱います。 -
67理学系化学物質の分析に利用される化学反応化学科
教授 横山 崇実験環境汚染、食品添加物などの問題を議論するにも犯罪捜査をおこなうにも物質の分析をおこなうということが必要です。それらのいろいろな物質を分析するために様々な化学反応が用いられています。それらの化学反応の多くは高校で習う簡単なものですが、化学反応系を選択することによって上手に物質の分析に利用されています。それらの化学反応の原理をいくつかの演示実験を通して解説します。
-
68理学系化学超解像顕微鏡で生体試料を観察する化学科
教授 酒井 誠講義光学顕微鏡は、生体試料観察に広く用いられていますが、光の回折限界による制限のために、本当に小さなもの(200 nm以下)を観察することはできませんでした。「超解像」顕微鏡はそんな制限を突破した極めて高い空間分解能を実現した顕微鏡であり、2014年にはノーベル化学賞にも輝きました。講義では、様々な種類の「超解像」顕微鏡の原理とその観察例について解説します。
-
69理学系化学金属錯体を繋げて作るナノ細孔物質化学科
教授 満身 稔講義
金属錯体は、中心金属イオンとそれを取り囲む配位子(有機物)から構成され、中心金属イオンの無機物としての特徴と配位子の有機物としての特徴を兼ね備えた物質であります。近年、金属イオンと配位子を配位結合で繋げたナノ細孔をもつ金属-有機構造体(MOF)あるいは多孔性配位高分子(PCP)とよばれる多孔性金属錯体の開発が盛んに行われています。このような物質を用いて、ガスの吸着、分離・精製、触媒作用だけでなく、磁性、電気伝導性、誘電性などの物性や光電変換など様々な目的で研究されています。本講義では、多孔性金属錯体について、その基礎と応用例について解説します。 -
70理学系化学周期表と元素のひみつ基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験全ての物質は元素からできています。私たちも物質なので、私たち自身も元素からできています。物質の世界を理解するためには、水素、炭素、窒素、酸素といった日本語元素名を知っていると便利です。では世界の人々と物質の話をするためには、外国語の元素名も知らなければいけないのでしょうか。元素名は、元素記号という世界共通の記号で書き表すことができます。その元素記号を、ある法則にしたがって美しく並べた表のことを周期表といいます。楽しい周期表のお話をしましょう。化学の楽しさ・奥深さを伝えます。演示実験あり。 https://www.gsakane.com/visiting.html
-
71理学系化学小さすぎる原子・分子・電子の世界基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験私たちが暮らす地球は大きすぎて、球であることは実感できません。しかし地球儀を見たり触ったり、宇宙から撮影した地球の画像を見れば、地球が丸いことを想像して実感できます。一方、私たちが暮らす世界は物質でできています。物質はつぶつぶの原子でできていますが、小さすぎて原子を粒として実感することは困難です。この講義・実験では、小さすぎて実感しにくい原子・分子・電子の不思議な世界を知り、想像して実感できるようにします。ミクロの不思議な世界を三次元可視化して示し、電気伝導、色、磁性の本質を伝えます。演示実験・生徒実験あり。 https://www.gsakane.com/visiting.html
-
72理学系物理学電子の軌道を三次元可視化して見てみよう!基盤教育センター
教授 坂根 弦太講義実験「化学基礎」にでてくる「電子の軌道」を三次元可視化して遊びましょう!K殻、L殻、M殻と1s軌道、2s軌道、2p軌道の関係も納得できるように説明します。5g軌道、6h軌道、7i軌道まで見てしまいましょう!原子軌道をガラス内部にレーザー彫刻したものを生徒様お一人一つずつ触っていただき、立体的な原子軌道を実感していただきます。もし、ごく普通のWindowsパソコンをご用意いただければ、周期表全ての元素の原子軌道、高校の教科書に出てくる分子の分子軌道を三次元可視化できる「教育用分子軌道計算システムeduDV」をインストールいたします。プログラムは(秀丸エディタがシェアウェアであることを除き)無償のもので、何台でもインストールしていただます。 https://www.dvxa.org/