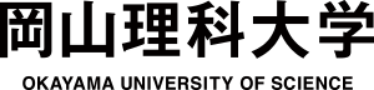-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
73理学系化学化学と生物の境界とは?
-DNAから新しい物を作る!-化学科
教授 山田 真路講義実験DNAと聞くと何を思い浮かべるでしょうか? 遺伝子? 生き物? お父さん・お母さん? ほとんどの人が生物に関する事柄を挙げると思いますが、DNAもペットボトルやプラスチックと同じ「高分子(小さな分子の集合体)」という化学物質です。ということは、DNAも何か新しい材料として利用できるのではないでしょうか? 本講義では高校の授業では生物として扱われているDNAを、化学の視点から切り込み、素材としてのDNAの可能性について説明します。また、簡単な実験を用いて、生物由来の高分子についての講義も行います。
-
74理学系化学光が関わる物質の変化化学科
准教授 若松 寛講義身のまわりにある物質の中には光によって変化するものが数多くあり、これらの化学反応を一般に光化学反応と呼びます。(デジカメでない)写真の感光や植物の光合成も鍵となる反応は光化学反応です。ここでは高校の化学では学ぶ機会の少ない光化学反応について、その一端に触れていきたいと思います。
-
75理学系化学次世代照明を支える“光る粉”化学科
教授 佐藤 泰史講義実験現在、白色LEDは次世代照明として大変注目されています。その理由は、既存の照明を白色LEDに置き換えることで大幅な省エネルギー化が期待できるからです。この白色LEDの実用化には、最近ノーベル賞受賞でも話題となった青色LEDの存在が挙げられます。しかしながら、白色LEDの実現には青色LEDと一緒に使われる“光る粉”も同じくらい重要です。“光る粉”=“蛍光体”は、古くから私達の身の回りでも多く使われています。この講義では、蛍光体の発光メカニズムについて実演を交えて解説するとともに、古代から現在までの利用されてきた経緯についても紹介します。
-
76理学系化学分子を超えた超分子の世界化学科
教授 岩永 哲夫講義超分子科学の分野において、近年注目されているトピックスの一つとして、2016年ノーベル化学賞の受賞対象となった分子マシンが挙げられます。分子マシンとは、ミクロあるいはナノスケールで制御された機械的動きをおこす分子、あるいは分子複合体のことを指します。この講義では、有機化学に関する基礎的なトピックスに加えて,これまでに報告されている様々な分子マシンと機能を紹介しながら、最新の研究トピックについてわかりやすく紹介します。
-
77理学系化学高分子と低分子が織りなす多様な機能・物性化学科
准教授 大坂 昇講義実験高分子は今や生活に欠かせない材料となり、日用品から最先端機能材料まで幅広く用いられています。しかし、実際に用いられている高分子の種類は意外に多くなく、高分子が有する階層構造を制御することで様々な機能・物性の利用が行われています。本講義では高分子(ポリビニルアルコール)と低分子との相互作用を通してスライム、スーパーボール、ビニロンスポンジ、偏光板等を適宜作製し、単一の高分子においても様々な機能・物性が発現することを実感してもらいます。
※講義時間は60分以上をお願いいたします。また、ガラス器具一式をお借りします。 -
78理学系化学環境と化学化学科
講師 川本 大祐講義地球は大気・水・土壌・生物から構成されており,これらの間で様々な物質が循環しています。人間による環境中への汚染物質の排出や自然破壊はこの物質循環を乱し,結果として環境問題を引き起こしていると考えられています。この物質循環を理解することは環境問題が起こった原因の究明や,解決策を考えるうえでのヒントになります。そこで,本講義では特に水と土壌との間でみられる物質の循環に焦点を当て,基本事項から最近の研究例についてわかりやすく紹介します。
-
79理学系化学赤外超解像を利用した生体試料の観察化学科
講師 高橋 広奈講義分子による赤外光の吸収を調べる手法(赤外分光)は、分子の構造や周囲の環境に関する重要な情報を与えてくれます。その一方で、①水が赤外光を吸収してしまうため水溶液での測定が難しい、②波長が長い赤外光を使うため微小な試料を観察することが不可能である、という欠点もあります。いくつかのレーザーを組み合わせることで、赤外に対して「超解像」を達成し、克服した観測手法が近年開発されています。講義では、赤外光を利用した観測手法の基礎と、「赤外超解像技術」の利用の実例を解説します。
-
80理学系化学静電気力と原子・分子基盤教育センター
教授 高原 周一講義実験静電気を使ったクイズ+演示実験を行い、静電気の基本的な性質を説明します。静電気が物体を引き付ける現象(静電誘導および誘電分極)を示し、全体としては電荷を持っていない原子・分子も内部に正負の電荷(原子核と電子)を含んでいることを説明します。電子レンジでの加熱実験を通じて、分子の極性についても説明します。化学結合も本質は静電気力であることも説明します。
-
81理学系化学電気を通すもの・通さないもの基盤教育センター
教授 高原 周一講義実験導通テスター等を使って身近な物体の電気伝導についてクイズ+演示実験の形式で調べていき、金属光沢をもったものは、基本的に金属であり良導体であることを確認します。同時に、金属酸化物はイオン結晶であり、一般的には良導体ではないことも示します。ポテトチップスの袋にはアルミ蒸着膜が使われていますが、その理由を説明し、金属の性質が身近なところで活用されていることを紹介します。また、金属の電気伝導と熱伝導の相関を示し、その両方が自由電子のはたらきによるものであることを説明します。
-
82理学系化学粒子論で理解する身近な現象のしくみ基盤教育センター
教授 高原 周一講義実験全ての物質は原子・分子といった粒子でできています。この考え方を使うと、様々な身近な現象を統一的に理解できます。このことを「気体を圧縮すると反発力がはたらくのななぜか」「食塩水をろ紙でろ過するとどうなるか」「食塩水の上に水を静かに注いで放置するととうなるか」といった基礎的な問題を考えながら実感してもらいます(一部の問題は演示実験あり)。その上で、気体の実体モデルやシミュレーションを提示し理解を深めます。また、原子論が正しいと認められるようになった歴史についても触れます。
-
84理学系化学化学反応の進む向きと自由エネルギー基盤教育センター
教授 高原 周一講義実験高校化学でエンタルピーおよびエントロピーを扱うようになりました。この講義では、一歩進んで自由エネルギーという量を導入し、化学反応が進む向きが自由エネルギーに支配されていることを説明します。自由エネルギーを使った議論で、温度変化に関するルシャトリエの原理、化学平衡の法則、イオン化傾向、相変化などの広範囲の法則・現象が説明できることを高校生にもわかるように示します。
※ 高校でエンタルピーとエントロピーを学習した生徒を対象とした内容です。 -
85理学系化学イオンと食べ物基盤教育センター
教授 高原 周一講義実験100V用の白熱電球を使ったテスターで電解質の水溶液が電気をある程度流すことを確認します。このテスターを使って、クイズ+演示実験の形式で、多くの食べ物の中にイオンが存在することを確認していきます。自然界の中でイオンが土壌→植物→動物→土壌と循環していること、植物の肥料の正体はイオンであることを説明します。有害なイオンがこの循環に入ることで公害が発生することにも触れます。
-
86理学系生物化学植物ホルモンの作用-植物の生存戦略生物科学科
教授 林 謙一郎講義実験脳や神経系をもたない植物は、環境変化に対して、オーキシン、ジベレリン、サイトカイニン、アブシジン酸、エチレンなどの植物ホルモンとよばれる低分子の有機化合物を体内で合成する。植物は、この植物ホルモンを成長調節物質として利用することで、温度、日照、水分、栄養などの環境要因に対して応答して自己の組織を環境に適応させて最適な成長形態をつくり上げる。本講義では、この植物ホルモンの作用-成長調節物質の全般を紹介する。
-
87理学系生物化学薬を創る生物科学科
教授 原村 昌幸講義新しい医薬品は、化学・生物の膨大な情報と最新の技術を駆使した「創薬」によって、長い年月と莫大な費用をかけて創り出されます。これらの医薬品創製に活用されている最新技術を紹介しながら、医薬品がどのように設計・合成されてゆくのかを概説し、「創薬」が医学・薬学だけではなく理学・工学・農学の知識・技術を集約した学問であることを説明します。
-
88理学系生物化学右手の分子と左手の分子生物科学科
准教授 窪木 厚人講義右手と左手は同じ作りをしてはいても、重ね合わせることはできません。小さな分子の世界にも“右手”と“左手”のような関係にあるものがありますが、必ずしもペアとして同じ数だけ存在するわけではなく、どちらか一方しか存在しない場合もあります。この講義では、これらの片寄りと生命現象、医薬品、食品添加物などとの関わりについて紹介します。
-
89理学系生物学外来生物ヌートリアって悪いヤツ?動物学科
教授 小林 秀司講義2005年の外来生物法の施行によって、ヌートリアは特定外来生物に指定され、悪い生物の代表として喧伝されているが、ヌートリアが日本に定着したのは二度にわたる国策増殖の失敗が原因である。また、生物学的に眺めると、きわめてユニークな特徴をたくさん持ち、意外ときれい好きな生きものであることも分かってきた。ヌートリアの過去・現在・未来についてわかりやすく講義したい。
-
90理学系生物学マウスがヒトの病気を治す?動物学科
教授 目加田 和之講義マウスはなぜ研究に使われているのでしょうか?もちろん理由があります。マウスはヒトと同じ哺乳類で、研究に便利な近交系やヒトの病気のモデル、最先端の遺伝子技術を使って作られたトランスジェニックやノックアウトマウスなど多くの種類があります。マウスはヒトの病気を治すための研究や遺伝子の働きを調べるために欠かせません。マウスがどんな動物なのか、どんな歴史を経てヒトに役立ってきたのか、わかりやすく解説します。
-
91理学系生物学栽培植物の名前と分類生物地球学科
教授 池谷 祐幸講義栽培植物は、食料などの資源のため、あるいは観賞するためという経済的、社会的な目的で人間が作りだし育てている植物です。このため野生植物とは異なり、名前の付け方や分類の仕方にも経済的、社会的な思惑が絡んできます。栽培植物の名前と分類を巡っての生物学と一般社会の狭間における不思議なルールの数々を紹介します。
-
92理学系生物学花粉から解き明かす過去の環境基礎理学科
准教授 藤木 利之講義現在の植生分布と気候の関係、および森林の構造、遷移についてお話し、後半には過去の環境を探る手法から、過去の環境変化、さらには人類の活動や移動についても紹介します。
-
93理学系生物学身近な昆虫を研究する生物地球学科
教授 中村 圭司講義私達の身の回りにはたくさんの昆虫がいます。これらの昆虫を観察していると、その生態について様々なことがわかってきます。また、人間活動を原因とした環境の変化が生物に与える影響などについても理解することができます。昆虫採集を中心とした簡単な研究から見えてくる、昆虫の世界についてお話します。