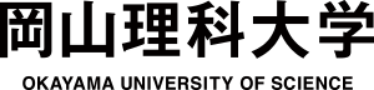-
講義番号大分類/小分類講義名・担当者講義種別講義内容第1希望第2希望第3希望
-
116理学系地球科学地球の中身 ~太陽系の果てより遠い足の下6400km~フロンティア理工学研究所
教授 畠山 唯達講義今や太陽系の端まで人工衛星が飛ぶ時代ですが、下に目を向けると、足元にあるたった数~数十kmの厚さの地殻すら掘り抜くことができていません。小学校~高校の理科(地学的分野)では地球の表層付近で起こる諸現象(地震・火山・気象など)を取り扱いますが、本講義ではもっと中の方についてお話しします。私たちの地球ができた46億年前から現在まで、内部と表層の環境、そして生物はどのように関わっているかも触れたいと思います。
-
117理学系天文学・宇宙科学現代の天文学生物地球学科
教授 福田 尚也講義最新の天文学の情報も提供しつつ、講義内容は高校からの要望に応じて行ないます。例えば、冥王星の降格(いかにして、冥王星は惑星から除外されたのか)、現代の宇宙観(太陽系から大規模構造)、現代の天体観測(ハワイの望遠鏡による天体観測)、星の誕生を探る、ブラックホールを探るなど、最新の天体画像をお見せしながら講義します。
-
118理学系天文学・宇宙科学高エネルギー宇宙線で見た宇宙の姿と流星観測基礎理学科
教授 伊代野 淳講義星が静かに輝く美しい夜空では、実は激しく活動的な高エネルギー原子核、素粒子現象が起こっていることが分かってきました。宇宙で繰り広げられる爆発現象やジェット現象を光速に近い速さで運動する粒子=宇宙線を通して見るとどのように見えるのか紹介します。
また、太陽系の彗星や小惑星は、流星や隕石として地球に到達することがあります。ほとんどは、上空50km以上のところで燃え尽きてしまいます。これが流星や火球です。流星や火球の観測を通した宇宙の物質の研究も紹介します。 -
119理学系天文学・宇宙科学隕石に記録された太陽系の形成・進化史
~顕微鏡で覗く太陽系の姿~基礎理学科
准教授 新原 隆史講義実験地球に落下する隕石には太陽系ができた約46億年前から現在までの記録が残されています。また、近年のサンプルリターンミッションにおいて、隕石と同様の物質が実在する天体から持ち帰られています。これらの宇宙物質を構成する基本単位である、「鉱物」について隕石の観察を通じて学び、隕石から読み解かれた太陽系の進化史について紹介します。
-
120理学系自然科学ダイヤモンドで見る高圧の不思議な世界基礎理学科
教授 森 嘉久講義実験ダイヤモンドは地球上で一番固い物質として知られています。そのダイヤモンドを使って超高圧の不思議な世界を案内いたします。身の回りの物質に圧力をかければ一体物質はどうなってしまうのかを自然科学の力で解明します。
また生物や食品などのソフトな材料から地球内部といったハードなものまで幅広い分野で活躍している高圧科学の一部も紹介します。 -
121理学系自然科学自然災害科学と防災の基礎基礎理学科
教授 鎌滝 孝信講義実験私たちが地球上で生活していく上で、地震、津波、洪水などが引き起こす自然災害との遭遇は避けて通れない事象と言えます。この講義では、地震、津波をはじめとした自然災害の発生メカニズムやその防災、減災についての基礎を学び、身のまわりの危険を正しく理解し、個々の防災意識を高めることを目的とします。また、私たちが身につけておきたい教養として、組織や地域における防災リーダーとしての考え方も養います。
なお、座学のみでなく半日~一日程度の野外実習を取り入れたより実践的なメニューにも対応可能です。 -
121理学系自然科学色にまつわるサイエンス
― 赤いルビーと青いサファイヤ ―フロンティア理工学研究所
教授 赤司 治夫講義実験私たちの周りには色があふれています。いったいどれくらいの色があるのか、数えてみようとしてもすぐにあきらめてしまうことでしょう。そうです、私たちは、毎日数えられないほどの多彩な色に囲まれて生活しているのです。では、私たちの周りにある「モノ」にはなぜいろいろな色がついているのでしょうか。その理由を探っていくとき、私たちは、とても小さなミクロの世界、原子や電子が繰り広げる美しい調和の取れた世界に突き当たります。さあ、みなさんの想像力をいっぱいにはたらかせて、物質に色をつける不思議な原子や電子の世界を探検に出かけましょう。
-
123理学系環境科学瀬戸内海をはじめとする西日本海域の水質
~ミニ実験:水質の測定をしてみよう~生物科学科
講師 宮永 政光講義実験瀬戸内海を中心として、太平洋などの外洋も含めた西日本海域の汚染状況について講義します。また、淡水域での水質汚染・生体試料を用いた水質汚染調査についても講義します。(ミニ実験として水質の簡易測定を行います。説明も含めて15分程度。)
-
125農・医療・生活科学系医療技術医療機器のスペシャリスト~臨床工学技士~医療技術学科
教授 堀 純也講義病院では数多くの医療機器が使用されています.臨床工学技士は呼吸・循環・代謝の分野を中心に医師の指示のもとに医療機器を操作して治療のサポートを行っています.本講義では,臨床工学技士の業務を中心に医療機器を用いた治療技術について解説します.
-
126農・医療・生活科学系医療技術電気現象を利用した心臓の観察と治療
~心電計やAEDの原理~医療技術学科
教授 堀 純也講義実験心臓は24時間365日、絶え間なく動いて血液を全身に送るポンプの働きをしています。この講義では、本物の心電計やAED(自動体外式除細動器)を用いた演示実験をしながら,心臓の動きと心臓の電気現象との関係について講義します(物理を履修していない学生さんにもわかるような講義構成にしています)。
-
129農・医療・生活科学系再生医学多能性幹細胞と再生医療生物科学科
教授 神吉 けい太講義病気やケガにより失われた体の機能を、細胞の力や組織の再生能力を使って回復させる医療が再生医療です。現在、体のどの細胞にも変化できる「万能細胞」を使った医療が実現しつつあります。ES細胞、iPS細胞などの多能性幹細胞と、それらを利用した再生医療の話題についてお話しします。
-
130農・医療・生活科学系医用工学医療に役立つ物理学医療技術学科
教授 堀 純也講義実験病院などの医療施設で使用されている医療機器の原理の理解や操作には、医学の知識だけでなく物理学の知識が大いに役立ちます。講義では、主に電気・光・音などの身近な物理現象を利用した実験を通して医療機器の原理などをやさしく紹介します(物理を履修していない学生さんにもわかるような講義構成にしています)。
-
131農・医療・生活科学系食物・栄養学食品中に含まれる生活習慣病治療薬の開発生物科学科
教授 松浦 信康講義実験食生活の変化に伴い、肥満、糖尿病、癌等の生活習慣病が増加しています。それらを予防するには、普段から、それらの発症を抑制する活性を有する食品を、積極的に摂取する必要があります。近年の細胞生物学、遺伝子工学技術を用いて、科学的に効果のある食を探索し、さらには医薬品開発に向けて、そのなかに含まれる活性本体の解明を行います。
-
132農・医療・生活科学系ブドウ栽培学日本ワインについて
-おもにワイン用ブドウ栽培について-ワイン発酵科学センター
准教授 川俣 昌大講義日本におけるブドウ栽培は、岡山県をはじめとする全国各地で国、県、大学等の研究機関で広く研究されています。しかし、そのほとんどが生食用ブドウについてで、ワイン用ブドウについてはほとんど試験研究が行われていません。一方、日本には全国各地にワイナリーが300近くあり、最近はワイナリーの数が急激に増えています。そこで岡山理科大学では、ワイン発酵科学センターを2017年に発足し、ワイナリーと連携協力してブドウとワインの品質がよくなるための地域の拠点となることをめざします。特にブドウ栽培について解説いたします。
-
133工学系機械工学SDGsとエコマテリアル機械システム工学科
教授 中川 惠友講義近年、地球温暖化対策と関連して世界的にCO2排出量削減が緊急の課題となっており、また、持続可能社会の発展(SDGs)を目的として地球資源の有効利用も重要となっています。軽量でリサイクル性の高いアルミニウム合金などの軽合金材料はエコマテリアル(地球環境に配慮した材料)として注目されています。本講義では、機械製品、エレクトロニクス、輸送機器、生活製品など多方面にてエコマテリアルの果たす役割をわかりやすく解説します。
-
134工学系機械工学工業を支える様々な材料の話機械システム工学科
教授 清水 一郎講義私たちの身の回りにある様々な機械や構造物は、全て固体材料でできていますが,使われている材料は物によって大きく異なります。実際のものづくりの場面では、どのように判断して材料を選んでいるのでしょうか?この講義では、様々な固体材料を紹介した後、材料の選び方やその基準について、例を挙げながら説明します。
-
136工学系機械工学機械製図のおもしろさ機械システム工学科
教授 中井 賢治講義実験飛行機や自動車などの工業用製品の安全設計のためには、それを構成する各部品の形状寸法を正しく決める必要があります。その形状寸法を基に実際に部品を製作をしなければいけませんが、複雑な形状寸法を言葉だけで製作者に伝えることは困難です。もし伝えることができたとしても、全く別の形状になってしまうかもしれません。このようなことが起こらないように、どのような形状を製作してほしいか図面として残す必要があります。ただ、自分では完璧な図面を描いたつもりでも、他の人が見た時にそれを理解できなければいけません。そのため、図面を描く人と見る人が共通の認識を持てるように、日本では日本工業規格(JIS)に従って図面の読み書きが行われています。実際に簡単な図面をJISに従って描いてもらい、機械製図のおもしろさを一緒に実感したいと思います。
-
138工学系ロボット工学ユニバーサルデザインと安全設計情報理工学科
教授 松浦 洋司講義実験ユニバーサルデザインの考え方によって、使いやすいものづくりが行われています。それに加えて、壊れにくく人に危害を与えない安全で安心なものづくりが不可欠です。これらを実現するには、使う人間のことを良く知らなくてはいけません。人間はどんなときに錯覚するのかなどについて説明し、ものづくりの上での注意点などを講義します。
-
139工学系ロボット工学ロボット工学とメカトロニクスの基礎と実演情報理工学科
教授 赤木 徹也
教授 藤本 真作講義実験身の周りの製品には、ロボット工学やメカトロニクス技術が数多く利用されています。携帯電話やお掃除ロボット、衝突被害軽減ブレーキ付きの自動車など、例を挙げればキリがないほどです。そこで本講義では、そうした製品やロボットを開発するうえで必要となる基礎的な技術について解説します。
また、これらの技術に関して、実機を用いた簡単な実験・体験を行い、ロボット工学・メカトロニクス技術の有用性を確認するとともに、それらを通して基礎知識の理解を深めます。 -
140工学系ロボット工学知能ロボットについて電気電子システム学科
教授 クルモフ バレリー講義実験ロボット技術がますます発展しており、産業界だけではなく日常生活においても普及しつつある。本講義では、まず、どんなものをロボットと呼ぶのか、また、 ロボットと様々な自動機械との違いを明確にします。また、ロボットの開発に係わる技術を分かりやすくを紹介し、動画などを用いて車輪型案内ロボットや自律飛行ロボットのデモンストレーションをします。